DTMなどの電子音楽と、WEB制作関連について
私たちのような、いわゆる「昔ながらのホームページ制作会社」に身を置いてきた人間からすると、ここ数年のノーコードブームは、驚きというより「いよいよ来たか」という感覚に近いものがあります。HTMLとCSSを手打ちし、テーブルレイアウトからスタートし、Flash全盛期を経て、WordPressが普及していく流れを見てきた世代にとって、制作の手法が変わること自体は、今に始まった話ではありません。
実際、技術は常に簡略化されてきました。Dreamweaverが出たときも、CMSが広まったときも、「誰でも作れる時代になる」と言われました。その延長線上に、今のノーコードツールがあります。ですから、ノーコードそのものを否定する気はありません。むしろ、制作工程の一部として見れば、非常によくできた仕組みだと思います。
ただし、制作会社の立場から見て、明らかに変わってしまったものがあります。それは「ホームページは作れば何とかなる」という認識が、以前よりも強くなってしまったことです。昔は、少なくとも「プロに頼まなければ作れないもの」でした。だからこそ、ヒアリングがあり、要件定義があり、構成案があり、その上でデザインやコーディングが進んでいました。工程として当たり前だったそれらが、ノーコードの普及によって、一気に省略されるようになりました。
制作会社として相談を受ける中で増えているのが、「自分たちで作ってみたが、全く反応がない」というケースです。
しかも、話を聞くと、決して手を抜いているわけではない。時間もかけているし、テンプレートも吟味している。文章もそれなりに考えて書いている。それでも成果が出ない。その原因を探っていくと、ほぼ例外なく「最初に設計されていない」という一点に行き着きます。
しかも、話を聞くと、決して手を抜いているわけではない。時間もかけているし、テンプレートも吟味している。文章もそれなりに考えて書いている。それでも成果が出ない。その原因を探っていくと、ほぼ例外なく「最初に設計されていない」という一点に行き着きます。
昔の制作会社の感覚で言えば、これは非常に分かりやすい話です。ホームページ制作は、画面を作る作業ではありません。誰に向けたサイトなのか、何を目的とするのか、どのページが入口になり、どこで問い合わせに至るのか。そうした流れを整理するところから始まる仕事です。
ところがノーコードでは、その「整理する工程」を飛ばして、いきなり画面を触れてしまう。これが最大の落とし穴です。
ところがノーコードでは、その「整理する工程」を飛ばして、いきなり画面を触れてしまう。これが最大の落とし穴です。
特に感じるのは、目的の曖昧さです。昔であれば、企業サイトなら企業サイトなりに、会社案内としての役割、営業資料としての役割、採用ツールとしての役割を分けて考えていました。
しかしノーコードで作られたサイトの多くは、それらがすべて混在しています。トップページに会社紹介、サービス説明、採用情報、代表メッセージが並び、結局何を一番伝えたいのか分からない構成になっている。制作会社から見ると、「これは設計段階で整理すべき話だ」と感じる場面が非常に多いのです。
しかしノーコードで作られたサイトの多くは、それらがすべて混在しています。トップページに会社紹介、サービス説明、採用情報、代表メッセージが並び、結局何を一番伝えたいのか分からない構成になっている。制作会社から見ると、「これは設計段階で整理すべき話だ」と感じる場面が非常に多いのです。
構造の問題も同様です。HTMLやCSSを理解してきた世代からすると、見出し構造やページ階層が曖昧なサイトは、どうしても気になります。ノーコードでは見た目を優先して編集できるため、見出しタグが装飾として使われたり、ページの主題がぼやけたりしがちです。検索エンジンの評価以前に、人が読んでも理解しづらい構造になっていることが少なくありません。
また、運用という観点が抜け落ちているケースも多く見受けられます。昔の制作会社では、「公開後にどう更新していくか」「誰が管理するのか」という話を必ずしていました。
ところがノーコードで作られたサイトの多くは、更新前提で設計されていません。結果として、最初に作った状態のまま何年も放置され、情報が古くなり、信頼性を落としてしまう。これは制作技術の問題ではなく、考え方の問題です。
ところがノーコードで作られたサイトの多くは、更新前提で設計されていません。結果として、最初に作った状態のまま何年も放置され、情報が古くなり、信頼性を落としてしまう。これは制作技術の問題ではなく、考え方の問題です。
制作会社として正直に言えば、「やはりプロに頼んだ方がいい」と言いたくなる場面は多々あります。ただし、それは仕事を取りたいからではありません。
一度でも本気でサイトを成果につなげようと考えたことのある制作側であれば、設計と戦略の重要性を痛いほど知っているからです。画面を組む作業は簡単になっても、考える作業は簡単になっていません。
一度でも本気でサイトを成果につなげようと考えたことのある制作側であれば、設計と戦略の重要性を痛いほど知っているからです。画面を組む作業は簡単になっても、考える作業は簡単になっていません。
ノーコードの普及によって、「ホームページ制作の価値が下がった」と感じる同業者もいるでしょう。しかし、長くやってきた立場から言えば、価値が下がったのは作業の部分だけです。むしろ、ヒアリング、整理、設計、方向性の提示といった部分の重要性は、以前より高まっています。そこに価値を見いだせるかどうかが、制作会社として生き残れるかどうかの分かれ目になっています。
成果が出ないノーコードサイトを見たとき、制作会社の人間は「やっぱりな」と思うと同時に、「まだ途中だ」とも感じます。設計を見直し、構造を整理し、目的を明確にすれば、十分に立て直せるケースが多いからです。昔ながらの制作会社が得意としてきたのは、まさにその部分です。
ノーコードの時代だからこそ、ホームページ制作の本質が問われています。作ること自体が簡単になった今、何を考え、どう設計し、どう成果につなげるか。その部分を語れる制作会社であり続けることが、これからの時代に求められているのではないでしょうか。
ノーコードホームページ制作の塩漬け化問題 成果に繋がらない90%の人が見落とす『最初の設計図』
ホームページ制作・修正、WEB制作関連について
PR
ここ数年、Web集客の現場で感じる一番の変化は「リスティング広告が効きにくくなった」という点だと思います。Google広告やYahoo!広告といった検索連動型広告は、かつてはROI(投資対効果)を測定しやすく、クリック単価(CPC)も低めに抑えられていました。しかし、今ではCPCが2倍3倍に上昇しているジャンルも珍しくありません。
特にBtoC向けの商材、たとえば美容・教育・不動産・飲食などでは、1クリックあたり数百円から千円を超えることもあり、広告費だけで月数十万円が消えていくケースも増えています。
この背景には、検索広告の枠そのものが限られていること、そしてAIによる自動入札が進んだ結果、競合が多いキーワードでは入札価格が高止まりしていることが挙げられます。つまり「どれだけ質の高いランディングページを作っても、そもそも広告が表示されにくい」状況になっているわけです。
コンテンツマーケティングも限界を迎えつつある
「広告がダメならSEOやコンテンツマーケティングで集客すればいい」と考える企業も多いですが、実はこの領域も以前のような効率が出にくくなっています。
GoogleのアルゴリズムがE-E-A-T(Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness)重視へと移行し、単に記事量を増やしても評価されにくくなりました。
さらに、生成AIの普及により、検索結果自体が要約・統合されてしまう傾向が強まり、「クリックされる検索結果」を作る難易度が上がっています。つまり、オーガニック検索の世界でも競争は激化し、従来型のSEOだけではリーチを広げられないのです。
このように、リスティング広告もSEOも頭打ちの状態の中で、いま多くの企業が次の手として注目しているのが「ショート動画」、特にTikTokの活用です。
TikTokがなぜ“広告を超えた接点”になるのか
TikTokの強みは、何よりも「ユーザーとの偶発的な出会い」が起きやすいことです。
アルゴリズムが興味関心ベースでコンテンツを推薦するため、フォロワーが少なくても再生数が伸びる可能性がある。つまり、初期段階でも爆発的なリーチを得られるチャンスがあります。
たとえば美容室や飲食店などでは、1本の動画が地域名とセットで拡散され、「この店行ってみたい」とリアル来店につながるケースが増えています。BGMの選定やテンポのよい編集、ナレーションや字幕の配置など、いわゆる「ネイティブ感」を保つ構成が効果的です。TikTokのユーザーは広告臭に敏感なので、プロモーションであっても自然に見える“共感導線”が求められます。
TikTok動画を軸にしたマーケティングの仕組み
TikTok単体で完結させるのではなく、Instagramや自社サイトとの連動が重要です。
TikTokは「発見」、Instagramは「信頼構築」、ホームページは「最終接点(コンバージョン)」という役割分担を意識します。TikTokで興味を持ったユーザーをInstagramのプロフィールや公式サイトに誘導し、詳細情報や口コミ、実績などを確認してもらう流れを作るのが理想です。
動画コンテンツの制作では、CTR(クリック率)やVTR(視聴完了率)、リテンション(平均視聴時間)などの指標をもとにPDCAを回す…と言いたいところですが、実際はTikTokでは「感情共鳴率」が何よりも重要です。つまり、数字よりも“共感が起きたかどうか”。
視聴者が「自分ごと」として感じた瞬間、コメントやシェアが一気に増え、アルゴリズムがさらに拡散を促します。
TikTok運用が特に向いている業種
全ての業種にTikTokが向いているわけではありません。
特に効果を出しやすいのは「ビジュアルで魅力を伝えられる業種」です。
たとえば美容院・ネイル・飲食・ファッション・スイーツ・フィットネス・エステ・インテリア・観光などは、映像映えする商材が多く、動画化によって視覚的な訴求が容易です。
また、採用やブランディング目的では、建築会社や製造業、整備工場などもTikTokと相性が良いです。製造工程や職人技、作業の“音”や“動き”がユーザーの好奇心を刺激します。
「普段見られない世界」を見せる動画はTikTok上で高く評価されやすく、視聴完了率が自然と上がります。
逆に、専門サービス(士業やBtoBのコンサルティングなど)では、TikTok単体でのリード獲得は難しいですが、「ブランド認知」や「会社の雰囲気紹介」には有効です。リクルート施策としてのTikTok運用は、近年急速に広まっています。
TikTok運用で成果を出すためのコツ
TikTokでは“綺麗すぎる動画”が必ずしも良い結果を生むとは限りません。
スマートフォンで撮ったリアルな映像や、少し崩した口調のナレーションの方がエンゲージメントを得やすい傾向があります。
つまり、完璧なブランディング動画よりも「親しみのある距離感」を演出することが、アルゴリズム的にも人間的にもプラスに働くということです。
また、動画の最初の3秒で“興味を引く構成”にすることが鉄則です。冒頭でオチを見せるくらいの勢いで、視聴者の注意をつかむ。そこから具体的なノウハウやビジュアルをテンポよく展開し、最後に自然なCTA(行動喚起)へつなげる構成を心がけます。
CTAは「詳しくはプロフィールから」や「○○で検索」など、押しつけがましくない導線が理想です。
SNS動画が“次のSEO”になる可能性
興味深いのは、TikTokが今や“検索プラットフォーム”として使われ始めている点です。
特にZ世代では「GoogleよりTikTokで検索する」という行動が一般的になりつつあります。
つまり、TikTok上の動画そのものがSEO的な位置づけを持ち始めているわけです。
動画タイトルやハッシュタグ設計も、従来のSEOのように戦略的に設計する必要があります。
このように、TikTokは単なる「SNS」ではなく、動画を中心にした“発見型検索メディア”へと進化しています。コンテンツマーケティングの一部としてTikTokを位置づけることで、従来のSEOと補完関係を築けるのです。
人の心を動かす集客は、もう検索だけじゃない
リスティング広告のクリック単価が高騰し、SEOの難易度も上がった今、企業が求めるべきは「人と人の感情がつながる接点」です。
TikTokやInstagramリールといったショート動画は、その接点を最短距離でつくるツールです。しかも、撮影機材も高価なものは不要で、アイデアと構成力があれば小さな店舗でも十分勝負できます。
結局、いまの時代に必要なのは「広告費をかける力」ではなく、「共感をつくる力」なのです。
その意味で、TikTokはリスティング広告や従来のSEOが届かない領域を切り開く、新しい集客の主戦場になりつつあると言えるでしょう。
リスティング広告効果が低下時に検討すべきSNS動画運用 TikTok・Instagramリール
ホームページ制作・修正、WEB制作関連について
企業の販促活動において、紙媒体とデジタル媒体はしばしば対立軸として語られることがあります。紙のチラシは古典的で一方向的、ホームページは現代的で双方向的といった捉え方です。しかし実際には、この二つを相互補完的に運用することで、単独では得られない相乗効果を生み出すことが可能です。
チラシは地域やターゲット層に対して直接的かつ即効性のあるアプローチを実現し、ホームページは情報量・拡張性・検索性に優れ、長期的な接点形成を可能にします。この両者を組み合わせることは、いわば「第一印象を担う接点」と「関係性を深める接点」をつなぐ戦略に他なりません。
チラシの役割:地域密着型のリアルな接点
チラシの最大の特徴は、エリアを限定した的確な訴求ができる点にあります。住宅街や駅周辺にポスティングする、商圏内で新聞折込を行う、イベント会場で配布するなど、物理的に対象者の手に渡る仕組みを構築できます。
また、チラシは触覚的な体験を伴います。紙の質感やデザイン、色彩は、情報を「単なるデータ」ではなく「所有できる物」として認識させ、記憶に定着しやすくします。家庭内で冷蔵庫に貼られたり机上に置かれたりすることで、日常生活に溶け込み、繰り返し視認される効果もあります。
ただしチラシには、情報量の制約や更新の困難さといった限界が存在します。ここで次の段階としてホームページが必要になります。
ホームページの役割:情報の深掘りと信頼形成
ホームページは、チラシが生み出した「興味関心」を次の行動へ導くプラットフォームとなります。
情報量の拡張
チラシに載せきれない詳細な商品情報、サービス内容、料金体系、写真や動画などを網羅的に掲載できます。来店前に雰囲気を確認できる360度写真や、導入事例・顧客の声といったコンテンツは、利用検討の意思決定を後押しします。
検索での発見可能性
SEOを考慮したホームページであれば、Google検索で新規顧客に発見される可能性が広がります。チラシでは接点を持てない遠方の顧客や、偶然検索した見込み客にも訴求できます。
即時性と更新性
キャンペーンや営業時間変更、在庫状況などをリアルタイムに反映可能です。印刷物では不可能なスピード感で情報を届けられるのは大きな利点です。
相乗効果の仕組み:クロスメディア戦略
チラシとホームページを組み合わせる戦略は、マーケティングにおける「クロスメディア戦略」として位置づけられます。異なる媒体が補完し合い、顧客行動の導線を多層的に設計できる点が強みです。
1. チラシが入口、ホームページが深掘り
チラシは短いキャッチコピーや画像で興味を喚起する役割を担い、QRコードや短縮URLでホームページに誘導します。ホームページ上で詳細情報を提示することで、購買や来店への意思決定を促進できます。
2. ターゲットの拡大
チラシは地域限定で「接点を確実に作る」役割を果たし、ホームページは検索やSNSを通じて「範囲を広げる」役割を果たします。両者を統合することで、ローカルから全国へと顧客層を広げることができます。
3. 信頼感の相互補強
紙媒体を通じた物理的な存在感と、デジタル上での豊富な情報量が組み合わさることで、「実在する事業体であり、かつ誠実に情報を提供している」という二重の信頼性を形成できます。
4. データ活用による改善
ホームページにアクセス解析を設置することで、チラシ経由の訪問数や行動履歴を把握できます。どのエリアの配布が効果的だったか、どの訴求文が反応を得たかといったデータを基に、次回以降の施策を最適化できます。
SEOとの連携:検索エンジン最適化の重要性
チラシとホームページをつなぐ際、ホームページ側のSEO設計は必須要素です。QRコードやURLで誘導できるのは「興味を持った人」に限られますが、検索経由で新規の見込み客を取り込むことで、販促の幅が大きく広がります。
ローカルSEO
「地域名+業種」のキーワードで上位表示されることは、チラシ配布エリアと相性が良いです。たとえば「○○市 パン屋」といった検索で露出すれば、紙媒体で接触した層と検索からの流入層を相互に補完できます。
構造化データの活用
営業時間や住所、レビュー評価などを検索結果に表示できるよう整備すれば、チラシで店名を知った人が検索した際に、即座に安心感を得られます。
コンテンツの継続的更新
チラシで誘導したユーザーが訪問した際に、情報が古かったり未整備だったりすると信頼を失います。SEO的な評価だけでなく、顧客体験の維持のためにも更新性は欠かせません。
SNSとの連携:シェアとコミュニケーションの強化
ホームページは静的な情報提供に適していますが、SNSは動的な情報発信とコミュニケーションに強みを持ちます。チラシからホームページに誘導し、さらにSNSに接続させる流れを設計することで、顧客接点を多層化できます。
拡散性の活用
チラシを受け取った顧客が、ホームページ経由でSNSアカウントをフォローする。そこから新商品情報やイベントをリアルタイムで受け取り、シェアによって二次的拡散が発生する。
信頼性の補完
ホームページが公式情報の拠点である一方、SNSは顧客との双方向コミュニケーションの場です。口コミやコメントのやり取りは、信頼感を高めると同時に、新規顧客に安心感を与えます。
キャンペーン連動
チラシに「SNSでこの投稿をシェアすると特典」と記載するなど、オフラインとオンラインをつなげる仕掛けも有効です。これによりチラシの一回性を超えて、継続的な接点へと発展させられます。
実際の活用シナリオ
例えば、新規開店する飲食店を想定してみます。
チラシ配布
開店1週間前から近隣住宅街に折込チラシを配布。メインビジュアルは料理の写真と「オープン記念割引」。QRコードを掲載し、ホームページへ誘導。
ホームページ展開
QRコード先のページでは、全メニュー、店内の雰囲気を伝える写真、予約フォームを完備。SEOを意識し「地域名+レストラン」で検索表示を狙う。
SNS連携
ホームページ内にInstagram・LINE公式アカウントへのリンクを設置。フォローした人に限定クーポンを配布。顧客が料理写真を投稿することで、自然な拡散効果が得られる。
結果として、チラシで来店動機を作り、ホームページで詳細情報を提供し、SNSでリピーター化を図る三段階の顧客導線が完成します。
統合的な販促戦略としての価値
チラシとホームページは、一見するとアナログとデジタルの対極にある存在ですが、戦略的に連携させることで極めて強力な販促効果を発揮します。チラシは「確実に接点を作る媒体」、ホームページは「深掘りと拡張を担う媒体」、さらにSEOとSNSを掛け合わせることで、「発見・拡散・信頼形成」を継続的に生み出すことができます。
単独の施策に依存するのではなく、各媒体の特性を理解し、全体の流れを設計することが、現代の販促活動における鍵です。紙媒体の持つリアルな訴求力と、デジタル媒体の持つ拡張力を融合させることで、企業は顧客との接点を多層的かつ持続的に確保できるのです。
チラシの効果が低下した時に行うホームページとのクロスメディア戦略
ホームページ制作・修正、WEB制作関連について
まず、「ナビゲーショナルクエリ」という言葉を簡単に整理しておきましょう。これはユーザーが検索エンジンで特定のブランド名や会社名、サービス名を入力して、その特定サイトに直接たどり着くことを目的とした検索行動のことを指します。例えば「スターバックス公式サイト」と検索する場合や、「○○製造会社 お問い合わせ」と入力する場合がこれに該当します。ユーザーはすでに行き先を明確に意識しているので、情報を探すというよりは、目的のウェブページにアクセスすること自体が目的です。
SEOの世界で言うと、ナビゲーショナルクエリは通常の「情報収集型クエリ」や「取引型クエリ」とは性質が違います。情報収集型クエリでは、ユーザーはまだ意思決定前で、役立つ情報を探しています。取引型クエリでは、購入や問い合わせを前提として検索しています。一方、ナビゲーショナルクエリは、すでに目的が決まっているので、SEOで上位表示を狙う戦略もやや変わります。ここで問題になるのが、いわゆる外部リンクを使った業者一覧ページです。
世の中には「特定の業種やサービスの業者をまとめました」と称して、外部リンクを並べただけのページが山ほどあります。たとえば「ホームページ制作会社一覧」や「○○修理業者一覧」といったページです。
これらは一見便利そうに見えますが、実際にはユーザーのナビゲーショナルニーズとはほとんど関係がありません。ユーザーが知りたいのは、一覧の存在ではなく、自分が問い合わせたい・契約したい業者に直接アクセスすることです。
これらは一見便利そうに見えますが、実際にはユーザーのナビゲーショナルニーズとはほとんど関係がありません。ユーザーが知りたいのは、一覧の存在ではなく、自分が問い合わせたい・契約したい業者に直接アクセスすることです。
こうした一覧ページのSEO戦略は、しばしば「外部リンクを大量に並べて、自サイトの評価を高める」というものです。しかし、これはユーザー体験を無視した典型的な手法です。Googleも近年のアルゴリズムアップデートで、ユーザーにとって有益なコンテンツかどうかをますます重視しています。外部リンクをただ並べるだけのページは、情報としての価値が低く、ナビゲーショナルクエリで上位表示を狙うのは非効率です。結果として、SEO的には無意味に近いリンク集が作られ、検索ユーザーの信頼も損なわれます。
さらに問題なのは、こうした業者一覧ページは、広告収入やアフィリエイト収益のために作られているケースが多いということです。リンク先の業者の質や信頼性は二の次で、SEO評価を稼ぐために外部リンクを集めることが主目的になっています。
その結果、ユーザーは「どれが本当に優良な業者なのか」を判断できず、ページを訪れても結局問い合わせや契約につながらないことが多いのです。ナビゲーショナルクエリを意図して検索しているユーザーにとっては、非常に不便で迷惑なページと言えるでしょう。
その結果、ユーザーは「どれが本当に優良な業者なのか」を判断できず、ページを訪れても結局問い合わせや契約につながらないことが多いのです。ナビゲーショナルクエリを意図して検索しているユーザーにとっては、非常に不便で迷惑なページと言えるでしょう。
SEOの専門家として言わせてもらうと、こうした一覧ページの存在は検索エンジンの本来の価値を下げる行為に近いです。ナビゲーショナルクエリを活用しているユーザーは、正確で信頼性のある情報を求めています。
しかしリンク集的ページは、その要件を満たさず、むしろノイズになってしまう。検索結果に表示されても、クリック率や滞在時間などのデータは低くなり、最終的にはSEO評価自体を下げる可能性があります。
しかしリンク集的ページは、その要件を満たさず、むしろノイズになってしまう。検索結果に表示されても、クリック率や滞在時間などのデータは低くなり、最終的にはSEO評価自体を下げる可能性があります。
また、外部リンクをただ集めるだけのページは、コンテンツの独自性がほぼゼロです。Googleは同じような一覧ページが乱立している状況を評価せず、むしろ順位を下げる傾向があります。結果として、運営者はリンク集のSEO効果を期待して作ったのに、逆に自社サイトの評価や信頼性を損なうリスクがあるわけです。ユーザーの検索意図やナビゲーショナルクエリを無視した安易なSEO手法は、もはや通用しません。
では、どうすればナビゲーショナルクエリに沿ったSEO施策が可能か。まず重要なのは、ユーザーが直接アクセスしたい情報を正確に提供することです。例えばホームページ制作会社なら、一覧ページではなく、各会社の特徴、得意分野、実績、問い合わせ窓口などを整理して提示する方が、ユーザーにとって価値があります。ナビゲーショナルクエリで上位表示されるページは、ユーザーが目的を達成しやすい構造と情報が整っているページです。
さらに、自社サイトの評価を高めたい場合は、無意味なリンク集ではなく、コンテンツの質と独自性に投資するべきです。例えば事例紹介、FAQ、ノウハウ記事、動画コンテンツなど、ユーザーにとって役立つ情報を発信すれば、自然と外部リンクも集まりやすくなります。これこそが、ナビゲーショナルクエリを活かしたSEO戦略であり、長期的に信頼を獲得する方法です。
外部リンクを使った業者一覧ページは、一見SEOの手段として使えそうに見えて、ユーザーの検索意図やナビゲーショナルクエリにはほとんど役に立たないという現実があります。クリックやアクセスを集めても、ユーザーの信頼や満足度は向上せず、結果としてSEO評価も伸びません。ナビゲーショナルクエリに対応するSEOは、リンク数ではなく、情報の正確性、独自性、利便性を基軸に設計することが必須です。
リンク集や業者一覧ページを作って「SEO対策しました」と言っている業者には注意が必要です。本当に効果的なオンライン戦略を求めるなら、ユーザー視点に立った情報設計とコンテンツの質を重視すべきであり、外部リンクを無理やり集める古い手法はもう時代遅れだと言わざるを得ません。ナビゲーショナルクエリを正しく理解し、ユーザーに寄り添ったSEOを実践することこそ、これからのWeb運営における本質的な戦略なのです。
ハブページ・ナビゲーショナルクエリとSEOの闇 表面的な「上位表示」が意図するもの
ホームページ制作・修正、WEB制作関連について
Googleは単なるキーワード一致ではなく、検索意図や文脈を理解する能力をAIで急速に高めています。特にBERTやMUMといった自然言語処理モデルは、単語単位ではなく文章全体の意味を把握します。そこで重要になるのが、文書の構造を正しく示すセマンティックHTMLです。正しくタグを使い分ければ、AIに対して「ここは見出し」「ここは定義」「ここは補足情報」といった文脈を伝えられます。
かつてはSEOといえば被リンク数やメタタグ調整に注目が集まりましたが、現在は検索アルゴリズムが構造や意味を解釈できるようになったため、セマンティックなマークアップそのものがコンテンツ評価の基盤になっています。
セマンティックHTMLの本質
技術的な観点では、見出しタグは単にキーワードを入れればよいのではなく、階層が論理的に整理されているかが重要です。AIは自然言語を理解するだけでなく、情報のレベル感や関連性を階層構造から学習するため、SEOの観点からも正しいマークアップが求められます。
構造化データとセマンティックHTMLの補完関係
セマンティックHTMLだけでは限界があり、補完的に利用されるのが構造化データ(JSON-LD)です。検索エンジンに対して「これは商品情報」「これはFAQ」「これはイベント情報」といった意味を機械可読形式で伝えることができます。
ただし、構造化データだけを付与しても、ベースのHTMLが非セマンティックでは評価されにくい傾向があります。つまりHTMLの正しい構造化と、構造化データの併用が検索最適化における両輪です。特に強調スニペットやリッチリザルトを狙う場合、両者を組み合わせて初めて成果が得られます。
アクセシビリティとSEOの交差点
セマンティックHTMLはアクセシビリティの基本でもあります。スクリーンリーダーは見出しやランドマーク要素をもとに読み上げ順を判断します。正しく構造化されていれば、視覚障害者も快適に利用でき、検索エンジンも文脈を理解しやすくなります。
Googleはユーザー体験を評価基準に含めているため、アクセシビリティ対応が結果的にSEOにもプラスに作用します。例えば代替テキスト(alt属性)を適切に付与すれば、画像検索での流入増加や、ページ全体の関連性向上につながります。
AI検索時代における差別化要素
AI検索が普及するにつれ、単なる文章の量やキーワード数では差別化が難しくなっています。検索結果が要約型に変化すると、コンテンツの「意味の正確さ」と「情報の信頼性」が評価軸になります。ここで差をつける要素がセマンティックHTMLです。
多くの競合サイトが表層的なデザインやテキスト量に依存するなか、意味論的なマークアップを徹底すれば、検索AIに「構造化された高品質な情報源」として認識されやすくなります。これが競合との差別化の核心です。
実装の注意点と落とし穴
セマンティックHTMLを導入する際の注意点は、見た目を優先して意味を犠牲にしないことです。例えばCSSで装飾すれば視覚的には見出し風に見えても、クローラはそれを見出しと判断しません。また、ランドマーク要素の乱用や誤用も逆効果になります。
さらに、JSで後からDOMを書き換える実装はレンダリング依存のため、検索エンジンが正しく理解できない場合があります。特に重要なコンテンツはサーバーサイドで直接セマンティックにマークアップするのが望ましいです。
セマンティックHTML Webページの論理構造の明確化で「意味」を構築
セマンティックHTMLは、単なるコーディング規則ではなく、AI時代のSEOに直結する技術基盤です。
検索エンジンに文脈を正しく伝える
構造化データと組み合わせて評価を強化する
アクセシビリティを高め、ユーザー体験を改善する
AI検索において競合と差をつける決定的要素になる
SEOにおける本質は「機械が理解できる形で人間に有益な情報を提示すること」です。その橋渡しとなるのがセマンティックHTMLであり、今後もWeb制作の中心的な技術であり続けるでしょう。
かつてはSEOといえば被リンク数やメタタグ調整に注目が集まりましたが、現在は検索アルゴリズムが構造や意味を解釈できるようになったため、セマンティックなマークアップそのものがコンテンツ評価の基盤になっています。
セマンティックHTMLの本質
セマンティックHTMLとは、見た目ではなく「意味」で要素を表すことです。例えば
<div>や <span><span> にスタイルを当てて見出しを作るのではなく、正しく</span></span>
<h1>~</h1>
<h6>を階層的に利用します。同様に、ナビゲーション部分は、主要本文は 、補足は、記事全体はといったタグで囲います。
これにより検索エンジンは「この部分がメインコンテンツ」「これは補助情報」という構造を機械的に理解できます。結果的に、重要なキーワードやテーマがより明確にクローラに伝わるため、ランキング評価に直結するのです。
見出しタグとSEOシグナル
見出しタグの正しい利用は特にSEOで大きな効果を持ちます。検索エンジンはをページの主題、</h6>
<h2>を大見出し、
<h3>以下をその補足とみなし、トピックの階層構造を判断します。誤った見出し構造は文書の意味を曖昧にし、検索エンジンにテーマが伝わらない原因になります。
技術的な観点では、見出しタグは単にキーワードを入れればよいのではなく、階層が論理的に整理されているかが重要です。AIは自然言語を理解するだけでなく、情報のレベル感や関連性を階層構造から学習するため、SEOの観点からも正しいマークアップが求められます。
構造化データとセマンティックHTMLの補完関係
セマンティックHTMLだけでは限界があり、補完的に利用されるのが構造化データ(JSON-LD)です。検索エンジンに対して「これは商品情報」「これはFAQ」「これはイベント情報」といった意味を機械可読形式で伝えることができます。
ただし、構造化データだけを付与しても、ベースのHTMLが非セマンティックでは評価されにくい傾向があります。つまりHTMLの正しい構造化と、構造化データの併用が検索最適化における両輪です。特に強調スニペットやリッチリザルトを狙う場合、両者を組み合わせて初めて成果が得られます。
アクセシビリティとSEOの交差点
セマンティックHTMLはアクセシビリティの基本でもあります。スクリーンリーダーは見出しやランドマーク要素をもとに読み上げ順を判断します。正しく構造化されていれば、視覚障害者も快適に利用でき、検索エンジンも文脈を理解しやすくなります。
Googleはユーザー体験を評価基準に含めているため、アクセシビリティ対応が結果的にSEOにもプラスに作用します。例えば代替テキスト(alt属性)を適切に付与すれば、画像検索での流入増加や、ページ全体の関連性向上につながります。
AI検索時代における差別化要素
AI検索が普及するにつれ、単なる文章の量やキーワード数では差別化が難しくなっています。検索結果が要約型に変化すると、コンテンツの「意味の正確さ」と「情報の信頼性」が評価軸になります。ここで差をつける要素がセマンティックHTMLです。
多くの競合サイトが表層的なデザインやテキスト量に依存するなか、意味論的なマークアップを徹底すれば、検索AIに「構造化された高品質な情報源」として認識されやすくなります。これが競合との差別化の核心です。
実装の注意点と落とし穴
セマンティックHTMLを導入する際の注意点は、見た目を優先して意味を犠牲にしないことです。例えばCSSで装飾すれば視覚的には見出し風に見えても、クローラはそれを見出しと判断しません。また、ランドマーク要素の乱用や誤用も逆効果になります。
さらに、JSで後からDOMを書き換える実装はレンダリング依存のため、検索エンジンが正しく理解できない場合があります。特に重要なコンテンツはサーバーサイドで直接セマンティックにマークアップするのが望ましいです。
セマンティックHTML Webページの論理構造の明確化で「意味」を構築
セマンティックHTMLは、単なるコーディング規則ではなく、AI時代のSEOに直結する技術基盤です。
検索エンジンに文脈を正しく伝える
構造化データと組み合わせて評価を強化する
アクセシビリティを高め、ユーザー体験を改善する
AI検索において競合と差をつける決定的要素になる
SEOにおける本質は「機械が理解できる形で人間に有益な情報を提示すること」です。その橋渡しとなるのがセマンティックHTMLであり、今後もWeb制作の中心的な技術であり続けるでしょう。
ホームページ制作・修正、WEB制作関連について
会社SNSでの一般スタッフの顔出し
会社のSNS運用において一般スタッフが顔出しをすることは、一見すると親しみやすさや社内の雰囲気を伝えられる効果があるように思えます。
実際、アットホームな企業文化を発信する目的で社員紹介や日常の様子を投稿している企業も少なくありません。しかしその一方で、一般スタッフの顔出しには見落とされがちなリスクが数多く存在しています。特に近年はSNSの拡散力が非常に強く、投稿内容が想定外の層に届いてしまうことも日常茶飯事です。
好意的な反応だけでなく、批判や悪意のあるコメント、さらには不正利用のリスクまで含めて考えなければならないのです。
第一に考えるべきは、プライバシー侵害のリスクです。スタッフの顔がSNS上に公開されるということは、その人物が特定の企業で働いていることが外部に知られることを意味します。これは必ずしも本人にとって望ましい状況ではなく、転職活動や私生活に影響を及ぼす可能性があります。
たとえば、職場以外の知人や家族に知られたくない場合や、副業規制のある職場で予期せぬ不利益を被る可能性もあります。さらに、個人名を出していなくても、顔写真からSNSのアカウントを特定されるケースや、AIによる顔認証技術を用いた検索で他のネット上の情報と紐づけられる危険性も無視できません。
第二に、セキュリティ面でのリスクも存在します。SNSに投稿された社員の写真から、職場の環境や機器、資料などの情報が思わぬ形で漏洩することがあります。背景に映り込んだ資料やパソコン画面、名札や社員証の一部が見えてしまうだけで、外部に重要な情報が流出する恐れがあります。さらに、社員個人がターゲットになるリスクもあります。詐欺や不審な営業勧誘、さらにはストーカー的な行為の対象になる可能性もゼロではありません。企業のブランド発信のために公開したはずが、社員個人の安全に直結するリスクを生んでしまうのです。
第三に、社内外の人間関係に影響するリスクも考えられます。顔出しをするスタッフとしないスタッフの間に温度差が生じ、社内の不公平感や不満につながることがあります。特にSNS運用担当者が恣意的に「映える社員」を選んで登場させると、他の社員から「なぜ自分は選ばれないのか」といった疑念が生まれる可能性があります。
また、外部から見た場合でも、特定の社員ばかりが登場することで、企業全体の印象が偏って伝わってしまいかねません。
第四に、炎上リスクです。SNSに投稿された社員の発言や行動が、意図せず炎上につながるケースは後を絶ちません。たとえば動画内での何気ない一言や、写真の背景にある要素が不適切と捉えられると、瞬く間に拡散され批判を浴びる可能性があります。この場合、批判の矛先は企業だけでなく、顔出しをした社員本人にも向けられるため、精神的な負担が極めて大きくなります。
さらに近年では、SNSの投稿内容が長期的に残り続けることも大きな問題です。
過去に社員紹介で顔出しをした写真が、数年後に本人のキャリアや人生の選択に悪影響を及ぼすことがあります。退職後に「元社員」として情報が残り続けることもあれば、転職先で意図せず過去の写真が見つかることもあります。インターネットに一度公開された画像は完全に削除することが難しいため、本人が望まなくても「デジタルタトゥー」として残ってしまうのです。
こうしたリスクを踏まえると、企業がSNSにおいて一般スタッフの顔出しを行う際には、十分な配慮が不可欠です。まずは本人の同意を明確に取り、将来的な利用範囲についても説明する必要があります。加えて、顔出しをせずに企業の雰囲気や日常を伝える方法も検討すべきです。たとえば手元や後ろ姿、イラストやキャラクターを活用するなどの方法であれば、プライバシーを守りながら雰囲気を伝えることができます。
社員の顔出しが本当に企業のブランディングに必要なのかを冷静に見極めることです。短期的な親しみやすさや人間味の演出を狙った結果、長期的なトラブルや社員の安全リスクを生むのであれば、それは企業にとって本末転倒と言わざるを得ません。SNSでの発信は企業イメージを高めるための有効な手段ですが、その裏側にあるリスクを正しく理解し、社員を守るという姿勢を第一に考えることが求められます。
ホームページやSNSでのスタッフの顔出しのリスク
会社のSNS運用において一般スタッフが顔出しをすることは、一見すると親しみやすさや社内の雰囲気を伝えられる効果があるように思えます。
実際、アットホームな企業文化を発信する目的で社員紹介や日常の様子を投稿している企業も少なくありません。しかしその一方で、一般スタッフの顔出しには見落とされがちなリスクが数多く存在しています。特に近年はSNSの拡散力が非常に強く、投稿内容が想定外の層に届いてしまうことも日常茶飯事です。
好意的な反応だけでなく、批判や悪意のあるコメント、さらには不正利用のリスクまで含めて考えなければならないのです。
第一に考えるべきは、プライバシー侵害のリスクです。スタッフの顔がSNS上に公開されるということは、その人物が特定の企業で働いていることが外部に知られることを意味します。これは必ずしも本人にとって望ましい状況ではなく、転職活動や私生活に影響を及ぼす可能性があります。
ホームページやSNSでスタッフの顔を出すことには、確かに多くの「光」、つまりメリットがあります。まず、何よりも信頼性の向上が挙げられます。
お客様は、企業のサービスや商品を利用する際に、どんな人が関わっているのかを知ることで、大きな安心感を得られます。顔が見えることで、会社全体へのイメージも向上し、これは私たちも日々の業務の中で強く実感しています。
そして、お客様との心理的な距離を縮める親近感の醸成も大きなメリットです。人間味あふれる投稿や、スタッフの人柄が垣間見えるコンテンツは、お客様が企業に対して「ファン」のような気持ちを抱くきっかけにもなります。
ホームページ上のコンテンツやSNS投稿における静止画はもちろん、特にInstagramやTikTokを中心とした動画配信はリーチ、インプレッション、そしてその集客効果が高い傾向にあります。
最近のSNSや検索エンジンのアルゴリズムが、人の顔が写っている投稿を優先的に表示する傾向にあるのも、こうした人間的なつながりが評価されているからでしょう。
さらに、採用活動においても、働く人の魅力や職場の雰囲気をダイレクトに伝えられるため、求職者にとって非常に魅力的に映り、入社後のミスマッチを減らす効果も期待できます。
実際に、私たちが支援させていただいた企業の中には、スタッフの顔出しを通じて集客やブランディングに大きく貢献し、目覚ましい成果を上げた成功事例もたくさん見てきました。
スタッフのプライバシー侵害
しかし、その「光」の裏側には、決して見過ごしてはならない「影」が潜んでいます。それは、軽視されがちなリスクの現実です。私たちホームページ制作やSNS運用に携わる者は、お客様企業の運用をサポートする中で、机上の空論ではない、実際に発生している深刻な問題に直面することが少なくありません。
スタッフのプライバシー侵害は、その最たる例です。顔出しによって個人が特定され、つきまといや無断転載、誹謗中傷といった被害に遭うケースを、残念ながら私たちは耳にしてきました。
たとえば、職場以外の知人や家族に知られたくない場合や、副業規制のある職場で予期せぬ不利益を被る可能性もあります。さらに、個人名を出していなくても、顔写真からSNSのアカウントを特定されるケースや、AIによる顔認証技術を用いた検索で他のネット上の情報と紐づけられる危険性も無視できません。
第二に、セキュリティ面でのリスクも存在します。SNSに投稿された社員の写真から、職場の環境や機器、資料などの情報が思わぬ形で漏洩することがあります。背景に映り込んだ資料やパソコン画面、名札や社員証の一部が見えてしまうだけで、外部に重要な情報が流出する恐れがあります。さらに、社員個人がターゲットになるリスクもあります。詐欺や不審な営業勧誘、さらにはストーカー的な行為の対象になる可能性もゼロではありません。企業のブランド発信のために公開したはずが、社員個人の安全に直結するリスクを生んでしまうのです。
第三に、社内外の人間関係に影響するリスクも考えられます。顔出しをするスタッフとしないスタッフの間に温度差が生じ、社内の不公平感や不満につながることがあります。特にSNS運用担当者が恣意的に「映える社員」を選んで登場させると、他の社員から「なぜ自分は選ばれないのか」といった疑念が生まれる可能性があります。
また、外部から見た場合でも、特定の社員ばかりが登場することで、企業全体の印象が偏って伝わってしまいかねません。
第四に、炎上リスクです。SNSに投稿された社員の発言や行動が、意図せず炎上につながるケースは後を絶ちません。たとえば動画内での何気ない一言や、写真の背景にある要素が不適切と捉えられると、瞬く間に拡散され批判を浴びる可能性があります。この場合、批判の矛先は企業だけでなく、顔出しをした社員本人にも向けられるため、精神的な負担が極めて大きくなります。
さらに近年では、SNSの投稿内容が長期的に残り続けることも大きな問題です。
過去に社員紹介で顔出しをした写真が、数年後に本人のキャリアや人生の選択に悪影響を及ぼすことがあります。退職後に「元社員」として情報が残り続けることもあれば、転職先で意図せず過去の写真が見つかることもあります。インターネットに一度公開された画像は完全に削除することが難しいため、本人が望まなくても「デジタルタトゥー」として残ってしまうのです。
こうしたリスクを踏まえると、企業がSNSにおいて一般スタッフの顔出しを行う際には、十分な配慮が不可欠です。まずは本人の同意を明確に取り、将来的な利用範囲についても説明する必要があります。加えて、顔出しをせずに企業の雰囲気や日常を伝える方法も検討すべきです。たとえば手元や後ろ姿、イラストやキャラクターを活用するなどの方法であれば、プライバシーを守りながら雰囲気を伝えることができます。
社員の顔出しが本当に企業のブランディングに必要なのかを冷静に見極めることです。短期的な親しみやすさや人間味の演出を狙った結果、長期的なトラブルや社員の安全リスクを生むのであれば、それは企業にとって本末転倒と言わざるを得ません。SNSでの発信は企業イメージを高めるための有効な手段ですが、その裏側にあるリスクを正しく理解し、社員を守るという姿勢を第一に考えることが求められます。
ホームページやSNSでのスタッフの顔出しのリスク
ホームページ制作・修正、WEB制作関連について
ホームページ制作後の修正は、ホームページ制作を行った制作会社に発注することが基本ですが、既にホームページ制作会社が廃業していることもあります。
制作後のホームページ修正は一見単純に見えても、実際には想像以上に複雑で専門性を伴う作業になることが少なくありません。
HTMLやCSSといった基本的なコード修正に加えて、CMSで構築されている場合にはテーマやプラグインのバージョン、さらにはサーバー環境まで影響することがあるため、単なるテキスト修正や画像差し替えであっても思わぬ不具合が発生するケースがあります。そのため、制作会社に依頼するのが理想ですが、すでに廃業している、または連絡が取れなくなっている場合には、外部の修正専門サービスを頼ることが現実的な解決策となります。
特に自作のホームページや、オーサリングツールで作られた古いサイトは、現在のブラウザやスマートフォン表示に対応しておらず、修正しようとしてもソフト自体がサポートを終了している場合があります。このような場合にはファイルを開いて内容を確認することすら難しく、修正よりもサイト全体の移行やリニューアルが推奨されることも少なくありません。
ワードプレスで構築されたサイトであっても、有料テーマや独自カスタマイズが施されている場合、コードの階層構造が複雑で、表面的な管理画面からでは修正できないケースも多々あります。結果として、単発の修正依頼であっても、内部構造を熟知した専門家に依頼する方が安全かつ確実です。
また、修正の範囲が限定的であれば単発対応で済みますが、頻繁に情報更新が必要な業種や、定期的なイベント・キャンペーンを告知するサイトであれば、単発対応よりも保守契約やサポート契約を結んだ方が結果的にコストパフォーマンスが良くなることもあります。単発修正は一回ごとに見積もりや工数確認が必要になるため、修正頻度が高いと納期が遅れたり費用が割高になる可能性があるからです。
修正依頼をする際には依頼内容を明確に伝えることが重要です。修正箇所のスクリーンショットを用意する、具体的なURLを示す、希望する文言や画像を事前に準備するなど、依頼する側の整理が行き届いているほど、スムーズかつ正確に対応してもらうことができます。逆に依頼内容が曖昧だと、不要なやり取りや工数が発生し、修正費用が膨らむ原因にもなります。
ホームページ制作後の修正は状況によって選ぶべき手段が変わります。制作会社が存在するならまずはそちらに依頼し、もし廃業や連絡不可であれば単発修正サービスを利用し、場合によってはリニューアルを検討するという流れが現実的です。
自作や無料サービスで制作したサイトであっても、いずれ更新や修正の段階で専門知識が求められる場面に直面するため、早い段階から修正サポートや移管を視野に入れておくことが、安定した運営につながるのです。
また自作のホームページやオーサリングツール、無料ホームページ、有料テーマ利用のワードプレスを利用したサイトなどの場合でも、ファイルが深部にあり自力では修正ができないことがあります。そうした場合は単発のホームページ修正サービスの利用となるでしょう。
ホームページ修正費用の相場と依頼
制作後のホームページ修正は一見単純に見えても、実際には想像以上に複雑で専門性を伴う作業になることが少なくありません。
HTMLやCSSといった基本的なコード修正に加えて、CMSで構築されている場合にはテーマやプラグインのバージョン、さらにはサーバー環境まで影響することがあるため、単なるテキスト修正や画像差し替えであっても思わぬ不具合が発生するケースがあります。そのため、制作会社に依頼するのが理想ですが、すでに廃業している、または連絡が取れなくなっている場合には、外部の修正専門サービスを頼ることが現実的な解決策となります。
特に自作のホームページや、オーサリングツールで作られた古いサイトは、現在のブラウザやスマートフォン表示に対応しておらず、修正しようとしてもソフト自体がサポートを終了している場合があります。このような場合にはファイルを開いて内容を確認することすら難しく、修正よりもサイト全体の移行やリニューアルが推奨されることも少なくありません。
ワードプレスで構築されたサイトであっても、有料テーマや独自カスタマイズが施されている場合、コードの階層構造が複雑で、表面的な管理画面からでは修正できないケースも多々あります。結果として、単発の修正依頼であっても、内部構造を熟知した専門家に依頼する方が安全かつ確実です。
また、修正の範囲が限定的であれば単発対応で済みますが、頻繁に情報更新が必要な業種や、定期的なイベント・キャンペーンを告知するサイトであれば、単発対応よりも保守契約やサポート契約を結んだ方が結果的にコストパフォーマンスが良くなることもあります。単発修正は一回ごとに見積もりや工数確認が必要になるため、修正頻度が高いと納期が遅れたり費用が割高になる可能性があるからです。
修正依頼をする際には依頼内容を明確に伝えることが重要です。修正箇所のスクリーンショットを用意する、具体的なURLを示す、希望する文言や画像を事前に準備するなど、依頼する側の整理が行き届いているほど、スムーズかつ正確に対応してもらうことができます。逆に依頼内容が曖昧だと、不要なやり取りや工数が発生し、修正費用が膨らむ原因にもなります。
ホームページ制作後の修正は状況によって選ぶべき手段が変わります。制作会社が存在するならまずはそちらに依頼し、もし廃業や連絡不可であれば単発修正サービスを利用し、場合によってはリニューアルを検討するという流れが現実的です。
自作や無料サービスで制作したサイトであっても、いずれ更新や修正の段階で専門知識が求められる場面に直面するため、早い段階から修正サポートや移管を視野に入れておくことが、安定した運営につながるのです。
また自作のホームページやオーサリングツール、無料ホームページ、有料テーマ利用のワードプレスを利用したサイトなどの場合でも、ファイルが深部にあり自力では修正ができないことがあります。そうした場合は単発のホームページ修正サービスの利用となるでしょう。
ホームページ修正費用の相場と依頼
ホームページ制作・修正、WEB制作関連について
AI生成コンテンツに対する検索エンジンの姿勢と、この混沌とした時代をどう生き抜くべきか、SEO(検索エンジン最適化)の専門性を極限まで高めて、Google検索の立場から。
ChatGPTGPT-5だの何だの、高性能AIが市場に投入されるたびに、Webの世界は「進化」だの「革命」だのと浮かれているが、そんな甘い言葉に騙されるな!俺から言わせりゃ、これは進化なんかじゃねぇ。SEOや検索エンジンとChatGPTのGPT-5について触れると、GeminiさんがGoogle検索エンジンの立場から本気でAIコンテンツ制作に喝を入れてくれるそうなので聞いてみました。あとSNSのアルゴリズム変動とAIコンテンツ対策についても熱く語っています。そんな中…Grokが登場します。
SEOや検索エンジンとChatGPT GeminiさんがAIコンテンツ制作に喝を入れてくれるそうです
ChatGPTGPT-5だの何だの、高性能AIが市場に投入されるたびに、Webの世界は「進化」だの「革命」だのと浮かれているが、そんな甘い言葉に騙されるな!俺から言わせりゃ、これは進化なんかじゃねぇ。SEOや検索エンジンとChatGPTのGPT-5について触れると、GeminiさんがGoogle検索エンジンの立場から本気でAIコンテンツ制作に喝を入れてくれるそうなので聞いてみました。あとSNSのアルゴリズム変動とAIコンテンツ対策についても熱く語っています。そんな中…Grokが登場します。
SEOや検索エンジンとChatGPT GeminiさんがAIコンテンツ制作に喝を入れてくれるそうです
ホームページ制作・修正、WEB制作関連について
ホームページ修正費用の相場と依頼。
弊社で制作させていただいたホームページの更新や修正も承っておりますが、ご自身で制作・運営されているホームページや、他社管理のホームページの更新作業、構成ファイルの修正も対応可能。

リンク修正、文言修正、単価修正等、、ページ内の画像設置、リンク設置・修正、ページ内でのレイアウト変更(ページの修正にあたり、画像設置などによって、ページ内のレイアウト変更が必要な場合は別途お見積)、ホームページのヘッダー情報(メタ設定)など、各種既存ページの修正に対応可能です。ページ本文はもちろんメニューやサイドバーなどの修正にも対応。
背景色や前景色(フォントカラー)の調整も可能です。
ホームページのページ更新やページ追加、ホームページ内部の様々な箇所の修正など、各種ホームページの更新・ホームページの修正の代行に対応しております。
ホームページの更新・修正料金 価格表・依頼方法
また自作のホームページやオーサリングツール、無料ホームページ、有料テーマ利用のワードプレスを利用したサイトなどの場合でも、ファイルが深部にあり自力では修正ができないことがあります。そうした場合は単発のホームページ修正サービスの利用となるでしょう。
次に、現状の問題点や課題も具体的に共有しましょう。単に「ここを直してください」ではなく、「スマートフォンでメニューが表示されない」「問い合わせフォームの入力項目が多すぎて離脱が多い」など、問題点を具体的に伝えることで、根本的な改善策を検討してもらいやすくなります。また、修正すべき箇所を特定する際には、対象ページのURLや画面キャプチャに加え、操作手順や発生条件を添えると精度が高まります。たとえば、「トップページのバナー画像(ヘッダー部分)」「お問い合わせフォーム送信後の確認メッセージ」など、どこで何がどうなっているかを明確に示すことが必要です。
修正完了後の検証方法や確認プロセスもあらかじめ決めておくべき事項です。テスト環境での確認を希望するのか、本番環境での最終チェックか、または特定のブラウザやデバイスでの動作検証が必要かなど、細かな条件も共有するとトラブル防止になります。
連絡手段やコミュニケーションフローも整理しておくことが効果的です。メールやチャットツール、プロジェクト管理システムのいずれを使うかを統一し、問い合わせ先や対応担当者を明示することで、情報の混乱や漏れを防ぎます。依頼内容は記録として残し、過去の修正履歴と照合できる状態にしておくことが重要です。修正依頼のログを保管することで、後から内容の確認や経緯の把握が容易になり、再発防止や運用改善に役立ちます。
ホームページの修正依頼を行う際には、「修正の目的と期待結果」「現状の課題」「対象箇所の特定」「具体的な修正内容」「優先度と納期」「検証方法」「連絡手段の統一」「依頼履歴の管理」といったポイントを体系的に伝えることが、作業効率と成果の質を高めるうえで欠かせません。これらを踏まえて連絡を行うことで、誤解や手戻りを減らし、円滑なサイト運営を実現できます。
トップページのスライド画像の位置を修正
恐らくはブラウザ側のレンダリング機能の修正?によるものと考えていますが、
実際のところの原因が把握できかねているため、
原因把握と修正を検討したく考えております。
一応CSSを修正することでこちらでもセンターに持っていくことは可能なのですが、
PC画面での表示の際に画像が横に伸びてしまうため従来の仕様(横伸びせずにセンター表示)に戻したく考えています。
WordPressのオリジナルテーマ、Liquidを使ったShopifyサイト、様々なサイト構築や方法に柔軟にご対応。
アニメーションが含まれるサイトも可。
web制作会社 某広告代理店様からLP案件
弊社で制作させていただいたホームページの更新や修正も承っておりますが、ご自身で制作・運営されているホームページや、他社管理のホームページの更新作業、構成ファイルの修正も対応可能。
リンク修正、文言修正、単価修正等、、ページ内の画像設置、リンク設置・修正、ページ内でのレイアウト変更(ページの修正にあたり、画像設置などによって、ページ内のレイアウト変更が必要な場合は別途お見積)、ホームページのヘッダー情報(メタ設定)など、各種既存ページの修正に対応可能です。ページ本文はもちろんメニューやサイドバーなどの修正にも対応。
背景色や前景色(フォントカラー)の調整も可能です。
ホームページのページ更新やページ追加、ホームページ内部の様々な箇所の修正など、各種ホームページの更新・ホームページの修正の代行に対応しております。
ホームページの更新・修正料金 価格表・依頼方法
ホームページ制作後の修正
ホームページ制作後の修正は、ホームページ制作を行った制作会社に発注することが基本ですが、既にホームページ制作会社が廃業していることもあります。また自作のホームページやオーサリングツール、無料ホームページ、有料テーマ利用のワードプレスを利用したサイトなどの場合でも、ファイルが深部にあり自力では修正ができないことがあります。そうした場合は単発のホームページ修正サービスの利用となるでしょう。
ホームページの修正依頼
ホームページの修正依頼をスムーズに進めるためには、伝えるべきポイントを整理し、正確でわかりやすい連絡を行うことが欠かせません。曖昧な指示や不十分な情報では、制作担当者が意図を正確に把握できず、手戻りや作業遅延の原因になりかねません。修正依頼時に押さえておくべき重要な連絡事項。修正内容の全体像とゴールを明示
まず、修正内容の全体像とゴールを明示することが重要です。どのような状態を目指しているのか、例えば「ユーザーが迷わず予約できる導線に変えたい」「キャンペーン情報を反映させて集客効果を高めたい」など、最終的な目的や期待効果を伝えると、制作側も作業方針を理解しやすくなります。次に、現状の問題点や課題も具体的に共有しましょう。単に「ここを直してください」ではなく、「スマートフォンでメニューが表示されない」「問い合わせフォームの入力項目が多すぎて離脱が多い」など、問題点を具体的に伝えることで、根本的な改善策を検討してもらいやすくなります。また、修正すべき箇所を特定する際には、対象ページのURLや画面キャプチャに加え、操作手順や発生条件を添えると精度が高まります。たとえば、「トップページのバナー画像(ヘッダー部分)」「お問い合わせフォーム送信後の確認メッセージ」など、どこで何がどうなっているかを明確に示すことが必要です。
サイト修正内容の詳細説明
修正内容の詳細説明も欠かせません。テキスト修正であれば具体的な文言の差し替え、画像の場合は差し替え用ファイルの提供や希望サイズの指定、機能改善なら動作フローや仕様の説明など、できる限り詳細に伝えます。曖昧な指示は誤解を生み、再修正の原因となるため注意が必要です。作業の優先順位や期限に関しても、明確に伝えておくことが望ましいです。すぐに対応が必要な修正なのか、他の作業とまとめて行ってよいのか、具体的なスケジュールを共有することで、担当者も効率よく作業計画を立てられます。修正完了後の検証方法や確認プロセスもあらかじめ決めておくべき事項です。テスト環境での確認を希望するのか、本番環境での最終チェックか、または特定のブラウザやデバイスでの動作検証が必要かなど、細かな条件も共有するとトラブル防止になります。
連絡手段やコミュニケーションフローも整理しておくことが効果的です。メールやチャットツール、プロジェクト管理システムのいずれを使うかを統一し、問い合わせ先や対応担当者を明示することで、情報の混乱や漏れを防ぎます。依頼内容は記録として残し、過去の修正履歴と照合できる状態にしておくことが重要です。修正依頼のログを保管することで、後から内容の確認や経緯の把握が容易になり、再発防止や運用改善に役立ちます。
ホームページの修正依頼を行う際には、「修正の目的と期待結果」「現状の課題」「対象箇所の特定」「具体的な修正内容」「優先度と納期」「検証方法」「連絡手段の統一」「依頼履歴の管理」といったポイントを体系的に伝えることが、作業効率と成果の質を高めるうえで欠かせません。これらを踏まえて連絡を行うことで、誤解や手戻りを減らし、円滑なサイト運営を実現できます。
トップページのスライド画像の位置を修正
恐らくはブラウザ側のレンダリング機能の修正?によるものと考えていますが、
実際のところの原因が把握できかねているため、
原因把握と修正を検討したく考えております。
一応CSSを修正することでこちらでもセンターに持っていくことは可能なのですが、
PC画面での表示の際に画像が横に伸びてしまうため従来の仕様(横伸びせずにセンター表示)に戻したく考えています。
バナーやWEBサイトの細かな修正
SNSで使用するバナーやWEBサイトの細かな修正など。デザインが得意なWEB制作会社。WordPressのオリジナルテーマ、Liquidを使ったShopifyサイト、様々なサイト構築や方法に柔軟にご対応。
アニメーションが含まれるサイトも可。
web制作会社 某広告代理店様からLP案件
ホームページ制作・修正、WEB制作関連について
ホームページの集客効果が低下する原因としてのSEOの側面
ホームページの集客効果が低下する原因をSEOに焦点を当てて捉えると、それは単なる検索順位の変動以上に、検索エンジンの評価アルゴリズムとの整合性の欠如に起因することが多くあります。特にGoogleはE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)を重視するようになり、実績や一次情報、独自の視点を持たないページは、順位を維持することすら困難です。表面的なSEO対策やキーワード密度だけでは評価されず、むしろ低品質コンテンツと判断されるリスクすらあります。SEOが機能しない原因の根本には「集客施策としてのSEO設計の欠如」があります。検索順位を上げること自体が目的化してしまい、その先にあるユーザー行動やコンバージョンに結びつかない設計になっていると、仮に一時的に上位表示されても、成果には結びつきません。SEOとは単なるテクニカルな手段ではなく、ユーザーと検索エンジン双方への価値提供を前提とした、戦略的なマーケティング活動であることを理解しなければ、持続的な集客は実現できないのです。
企業ホームページの目的としては「ホームページを利用した集客」となりますが、そうした目的自体を達成するためには通常のマーケティングと同様にどういった内容の問い合わせをどういった流れで獲得するのかを検討していく必要があります。
技術的な要因も無視できません。内部SEOの劣化、つまりタイトルタグやディスクリプションの最適化不足、パンくずリストの構造不備、canonicalタグの誤用、さらにはJavaScript依存によるインデックスブロックなど、構造的な問題が蓄積していると、Googlebotのクロール効率が下がり、検索エンジン上での認識そのものが正確に行われなくなります。サイト全体のクロールバジェットを消費しやすくなるため、特に中〜大規模なサイトでは影響が顕著です。
さらに、コンテンツの同質化・重複性が深刻な問題です。他サイトと似たような内容や構成、表現をしているページは、Googleによって「価値のない複製コンテンツ」と見なされる可能性があります。特にChatGPTなどの生成系ツールを用いた大量コンテンツ投入が一般化する中で、独自性のある見解、一次情報、具体的な事例や体験談がないページはSEO的に淘汰されつつあります。構造化データのマークアップや、FAQリッチリザルトの最適化も、情報の意味を検索エンジンに伝えるうえで不可欠です。
さらに、モバイル対応の甘さも影響します。Googleはモバイルファーストインデックスを採用しており、スマホでの表示に不具合がある、クリック可能要素が小さすぎる、フォントサイズが読みづらいといった問題は、即座にSEOスコアの低下に反映されます。モバイルページがPCとは異なる構成になっている場合、重要な情報がクローラに届かないリスクもあります。
ホームページで集客できない理由 その原因と対策
集客効果のあるホームページを制作するということを考えた時には、Webデザインが美しいものであることは必須要素ではありません。また、SEOによって検索結果順位を向上させるということも部分的です。
ただ、ヘルプフルコンテンツアップデートが実施され、本格的にAI(人工知能)が検索エンジンに導入されてから以降は、ページの品質が検索結果にも大きく影響を与えています。
ホームページの集客効果が低下する原因をSEOに焦点を当てて捉えると、それは単なる検索順位の変動以上に、検索エンジンの評価アルゴリズムとの整合性の欠如に起因することが多くあります。特にGoogleはE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)を重視するようになり、実績や一次情報、独自の視点を持たないページは、順位を維持することすら困難です。表面的なSEO対策やキーワード密度だけでは評価されず、むしろ低品質コンテンツと判断されるリスクすらあります。SEOが機能しない原因の根本には「集客施策としてのSEO設計の欠如」があります。検索順位を上げること自体が目的化してしまい、その先にあるユーザー行動やコンバージョンに結びつかない設計になっていると、仮に一時的に上位表示されても、成果には結びつきません。SEOとは単なるテクニカルな手段ではなく、ユーザーと検索エンジン双方への価値提供を前提とした、戦略的なマーケティング活動であることを理解しなければ、持続的な集客は実現できないのです。
企業ホームページの目的としては「ホームページを利用した集客」となりますが、そうした目的自体を達成するためには通常のマーケティングと同様にどういった内容の問い合わせをどういった流れで獲得するのかを検討していく必要があります。
検索意図(サーチインテント)との整合性
SEOでの可視性を確保するには、検索意図(サーチインテント)との整合性が不可欠です。ユーザーが入力するキーワードの背後にある本当のニーズを読み取り、それに応じた情報構成やコンテンツ設計を行う必要があります。にもかかわらず、多くのサイトは過去に流行したキーワードの詰め込みや、テンプレート型の記事ばかりを量産してしまい、Googleからの評価を落としています。技術的な要因も無視できません。内部SEOの劣化、つまりタイトルタグやディスクリプションの最適化不足、パンくずリストの構造不備、canonicalタグの誤用、さらにはJavaScript依存によるインデックスブロックなど、構造的な問題が蓄積していると、Googlebotのクロール効率が下がり、検索エンジン上での認識そのものが正確に行われなくなります。サイト全体のクロールバジェットを消費しやすくなるため、特に中〜大規模なサイトでは影響が顕著です。
コアウェブバイタル(LCP・FID・CLS)
コアウェブバイタル(LCP・FID・CLS)などのページエクスペリエンス指標の悪化も、SEO順位の低下に直結します。表示速度が遅く、視覚的安定性に欠けるページは、Googleの評価だけでなく、ユーザー体験にも悪影響を及ぼし、結果的に直帰率や離脱率の上昇につながります。これは検索エンジンのシグナルとして取り込まれ、SEOスコアが下がる要因となります。さらに、コンテンツの同質化・重複性が深刻な問題です。他サイトと似たような内容や構成、表現をしているページは、Googleによって「価値のない複製コンテンツ」と見なされる可能性があります。特にChatGPTなどの生成系ツールを用いた大量コンテンツ投入が一般化する中で、独自性のある見解、一次情報、具体的な事例や体験談がないページはSEO的に淘汰されつつあります。構造化データのマークアップや、FAQリッチリザルトの最適化も、情報の意味を検索エンジンに伝えるうえで不可欠です。
外部要因との連携の弱さ 被リンクの獲得が極端に少ない、サイテーション(言及)数がない
SEOでは外部要因との連携の弱さも無視できません。被リンクの獲得が極端に少ない、サイテーション(言及)数がない、ソーシャルシェアがゼロという場合、検索エンジンはそのサイトを「社会的に評価されていない」と判断します。特にローカルSEOにおいては、NAP情報の統一やGoogleビジネスプロフィールとの連携がSEO評価に影響するため、整備不足が原因でローカル検索から弾かれる事例も散見されます。さらに、モバイル対応の甘さも影響します。Googleはモバイルファーストインデックスを採用しており、スマホでの表示に不具合がある、クリック可能要素が小さすぎる、フォントサイズが読みづらいといった問題は、即座にSEOスコアの低下に反映されます。モバイルページがPCとは異なる構成になっている場合、重要な情報がクローラに届かないリスクもあります。
ホームページで集客できない理由 その原因と対策
集客効果のあるホームページを制作するということを考えた時には、Webデザインが美しいものであることは必須要素ではありません。また、SEOによって検索結果順位を向上させるということも部分的です。
ただ、ヘルプフルコンテンツアップデートが実施され、本格的にAI(人工知能)が検索エンジンに導入されてから以降は、ページの品質が検索結果にも大きく影響を与えています。
ホームページ制作・修正、WEB制作関連について
自社のWebサイト運営を新たに引き継ぐ立場になった場合、最初にぶつかる壁は「何が、どこまで、誰によって管理されているのかが見えない」という不透明さです。特に前任者が急な退職だった場合には、引き継ぎ資料が残っておらず、ドメインやサーバーの情報すら把握できていないというケースも少なくありません。私はそうした状況の中でWeb担当者に任命され、まず行ったのは、ホームページが何によって構成されているのかをひとつひとつ確認する作業でした。
運用体制を整える一方で、バックアップの自動化も必須です。WordPressのバックアッププラグインを導入し、週1回のデータベースとファイルの自動バックアップを設定。外部ストレージとの連携も行い、万が一サイトが破損した際にも迅速に復旧できる環境を作りました。これにより、社内からの信頼も高まり、トラブル時にも慌てず対応できるようになりました。新たにWeb担当となると、つい見た目やデザインの刷新を先に考えがちですが、まずは足元を固めることが最重要です。ドメインとサーバーの契約状態を確認し、すべてのログイン情報を一元管理し、管理権限の所在を明確にすることで、Web担当者としての責任を果たす土台が整います。そのうえで、保守・更新のフローを仕組みとして組み立てていくことで、前任者に頼りきっていた旧体制から脱却し持続可能なWeb運用が可能になります。
Web担当者がいなくなりホームページの情報がわからない場合の対処法
ホームページの日々の更新と継続的な管理
ホームページは一度作って終わりではなく、日々の更新と継続的な管理によって企業の資産となります。担当者が変わっても情報が失われない仕組みこそが、これからのWeb活用の基盤となるのです。私はこの経験を通じて、個人の能力だけに依存しない体制づくりの大切さを痛感しました。そして今、新たにWeb担当者となった方に、まず最初にやるべきことは「すべてを知ろうとすること」ではなく、「何が分かっていて、何が分からないかをはっきりさせること」だとお伝えしたいです。それが、混乱を整理し、次に進むための第一歩となります。ホームページがWordPressで構築されているかどうか
現在のホームページがWordPressで構築されているかどうかを確認するのは最初の一歩です。ログイン画面が表示でき、管理者アカウントでダッシュボードに入れる状態であれば、内部の状況を詳細に調べることができます。テーマの構成、プラグインの種類、更新状況、バックアップの設定状況、連携しているGoogleサービスなど、基本構成の把握がここで可能になります。もしログインできない場合は、社内に残っている情報からログイン情報を探したり、ブラウザのパスワード記録を確認したり、過去の担当者のメール履歴などを頼りにサーバーやドメインの管理元を特定する必要があります。サーバーもドメインも前任者の個人メールで契約
私が担当になったとき、サーバーもドメインも前任者の個人メールで契約されており、情報変更すらできない状態でした。このような場合、契約先のサポート窓口に連絡し、法人名義の証明書や在籍証明書などを提出することで、名義変更やパスワード再発行を進めることができます。WordPressの内部にもアクセスできなかったため、まずはFTPやデータベースへの接続情報を調査し、必要に応じて外部の専門会社にサポートを依頼しました。前任者のIDや個人メールが管理者アカウントとして残っている
新しい担当者が気を付けなければならないのは、前任者のIDや個人メールが管理者アカウントとして残っていることです。この状態では、セキュリティ的に極めて脆弱であり、不正アクセスやトラブルの温床となりかねません。まずは現在の管理者アカウントを確認し、新たな管理者用アカウントを発行して、旧アカウントは削除または権限変更する必要があります。さらに、不要なプラグインや更新されていないテーマなどが放置されていれば、それも速やかに見直し、安全な構成に再設計すべきです。ホームページの保守管理体制が整っていなかった場合
また、ホームページの保守管理体制が整っていなかった場合には、外部の管理会社との契約を検討しました。内部で技術対応が困難な場合や、突発的な不具合に即時対応できる体制がない会社にとって、信頼できる管理会社との契約はホームページ運用の安定化に直結します。私の場合、WordPressの保守、定期バックアップ、障害時対応、セキュリティチェックなどを委託し、自社では日々の情報更新に集中する体制を構築しました。運用体制を整える一方で、バックアップの自動化も必須です。WordPressのバックアッププラグインを導入し、週1回のデータベースとファイルの自動バックアップを設定。外部ストレージとの連携も行い、万が一サイトが破損した際にも迅速に復旧できる環境を作りました。これにより、社内からの信頼も高まり、トラブル時にも慌てず対応できるようになりました。新たにWeb担当となると、つい見た目やデザインの刷新を先に考えがちですが、まずは足元を固めることが最重要です。ドメインとサーバーの契約状態を確認し、すべてのログイン情報を一元管理し、管理権限の所在を明確にすることで、Web担当者としての責任を果たす土台が整います。そのうえで、保守・更新のフローを仕組みとして組み立てていくことで、前任者に頼りきっていた旧体制から脱却し持続可能なWeb運用が可能になります。
Web担当者がいなくなりホームページの情報がわからない場合の対処法
ホームページ制作・修正、WEB制作関連について
ホームページ(サイト)のドメイン・URLを変更する場合の作業。ホームページのドメイン(URL)は、あまり積極的には行われませんが、企業ホームページなどにおいて社名変更等によってサイト内容の名称部分の変更と合わせてドメインを変更する場合があります。独自ドメインの変更を行う場合、同一サーバー内で実施する場合と、サーバーも移転する場合とで、作業量が異なります。
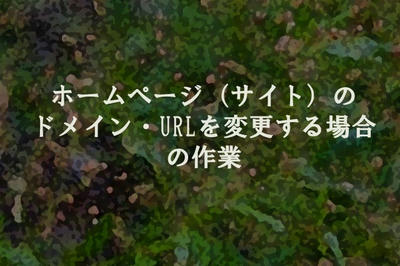
こうしたドメイン(URL)変更の際に必要となる作業の概要
ホームページのドメイン(URL)変更
ホームページやウェブサイトのドメインおよびURLを変更する場合には、慎重な作業と計画が必要です。ドメインやURLは検索エンジンの評価やユーザーのアクセスに大きく影響を与えるため、不適切な変更はSEO順位の低下やアクセス減少を招くことがあります。
まず、変更作業に入る前に現在のサイトの状況を詳細に把握することが重要です。Googleサーチコンソールやアクセス解析ツールで、現行のURL構造や主要な流入経路、検索順位の高いページを洗い出します。この情報をもとに、新しいドメインやURL構造の設計を行います。URLはできる限り意味のあるパス構造にし、ユーザーにわかりやすく、検索エンジンにも適切に認識されやすいものを心がけます。
URL変更に際して最も重要な作業はリダイレクト設定です。旧URLから新URLへの恒久的なリダイレクト(301リダイレクト)をサーバー側で設定し、検索エンジンやブラウザに新しい場所を正しく伝えることが求められます。これにより、旧ドメインや旧URLに蓄積されたSEO評価を新しいURLに引き継ぐことが可能です。Apacheなら.htaccess、Nginxなら設定ファイルで一括リダイレクトルールを作成するのが一般的です。リダイレクトは全ページに対して適切に設定し、誤ったリダイレクトやループを避けることが重要です。
また、Googleサーチコンソールの「住所変更ツール」を利用して、ドメイン変更の申請を行います。これにより、Googleに対して新しいドメインへの切り替えを公式に通知し、インデックスの移行をスムーズに進められます。旧ドメインのサーチコンソールと新ドメインの両方で管理権限を持つ必要があります。
DNS設定の切り替え後は、キャッシュクリアやDNSの伝播状況を確認しながら段階的にアクセス状況を監視します。Googleアナリティクスやその他の解析ツールの設定も新ドメインに合わせて修正を忘れてはいけません。
ドメイン変更後も一定期間は旧URLに対するリダイレクトを維持し続けることが重要です。これにより、既存のユーザーや検索エンジンのクローラーが新しいURLにアクセスできるようになります。期間は最低でも6か月から1年を目安にするとよいでしょう。
独自ドメイン(URL)の変更とDNS設定
同一サーバー内であれば、ドメイン登録後にDNS設定を行い、今まで使用していたディレクトリパスと紐付けることで、独自ドメイン(URL)の変更を行うことができます。ただ、サイトデータ内のURLパス、内部リンクのリンクパスは変更する必要があります。ホームページのドメイン(URL)変更を行う場合は、DNSの反映時間等を含め、見落としている点はないかを常に確認し、慎重に作業をしていく必要があります。こうしたドメイン(URL)変更の際に必要となる作業の概要
ホームページのドメイン(URL)変更
ホームページやウェブサイトのドメインおよびURLを変更する場合には、慎重な作業と計画が必要です。ドメインやURLは検索エンジンの評価やユーザーのアクセスに大きく影響を与えるため、不適切な変更はSEO順位の低下やアクセス減少を招くことがあります。
ドメイン・URL変更時の具体的な作業手順と注意点について
ホームページのドメインやURLを変更する場合は、事前の現状分析、DNSおよびサーバー環境の整備、301リダイレクトの適切な設定、検索エンジンへの通知、内部リンクとサイトマップの更新、外部リンク対応、解析ツールの設定変更、そしてリダイレクトの継続運用を含む一連の作業を漏れなく丁寧に行う必要があります。これらを怠ると、検索順位の大幅な低下やアクセス減少、ユーザーの離脱を招きかねません。専門的な知識と慎重な対応が求められるため、場合によっては専門の制作会社やSEOコンサルタントに依頼することも検討すべきでしょう。まず、変更作業に入る前に現在のサイトの状況を詳細に把握することが重要です。Googleサーチコンソールやアクセス解析ツールで、現行のURL構造や主要な流入経路、検索順位の高いページを洗い出します。この情報をもとに、新しいドメインやURL構造の設計を行います。URLはできる限り意味のあるパス構造にし、ユーザーにわかりやすく、検索エンジンにも適切に認識されやすいものを心がけます。
新ドメイン取得やホスティング環境の準備
次に、新ドメイン取得やホスティング環境の準備を行います。ドメイン移管の場合はドメインレジストラでの手続きも同時に進めますが、DNSの浸透には最大で72時間程度かかることを想定し、切り替えのタイミングを慎重に調整します。URL変更に際して最も重要な作業はリダイレクト設定です。旧URLから新URLへの恒久的なリダイレクト(301リダイレクト)をサーバー側で設定し、検索エンジンやブラウザに新しい場所を正しく伝えることが求められます。これにより、旧ドメインや旧URLに蓄積されたSEO評価を新しいURLに引き継ぐことが可能です。Apacheなら.htaccess、Nginxなら設定ファイルで一括リダイレクトルールを作成するのが一般的です。リダイレクトは全ページに対して適切に設定し、誤ったリダイレクトやループを避けることが重要です。
また、Googleサーチコンソールの「住所変更ツール」を利用して、ドメイン変更の申請を行います。これにより、Googleに対して新しいドメインへの切り替えを公式に通知し、インデックスの移行をスムーズに進められます。旧ドメインのサーチコンソールと新ドメインの両方で管理権限を持つ必要があります。
サイト内の内部リンクもすべて新URLに書き換える
サイト内の内部リンクもすべて新URLに書き換える必要があります。CMSを利用している場合は一括置換機能を活用するか、専門のプラグインを導入すると効率的です。手動での書き換えはミスの原因になるため注意が必要です。さらに、サイトマップ(XML形式)を新URLに対応させて作成し、サーチコンソールに再送信してインデックス促進を図ります。外部リンクの問題
特に被リンク元の重要なサイトには、新URLへの変更を通知し、可能な範囲でリンク先の修正を依頼することが望ましいです。すべての外部リンクを書き換えるのは現実的に難しいため、リダイレクト設定でカバーする形となりますが、主要なリンク元に対応してもらうことはSEO効果の維持に役立ちます。DNS設定の切り替え後は、キャッシュクリアやDNSの伝播状況を確認しながら段階的にアクセス状況を監視します。Googleアナリティクスやその他の解析ツールの設定も新ドメインに合わせて修正を忘れてはいけません。
ドメイン変更後も一定期間は旧URLに対するリダイレクトを維持し続けることが重要です。これにより、既存のユーザーや検索エンジンのクローラーが新しいURLにアクセスできるようになります。期間は最低でも6か月から1年を目安にするとよいでしょう。
ホームページ制作・修正、WEB制作関連について
双ヶ丘は、高度116 mという低山ながらその地形と歴史的遺構、豊かな自然が絶妙に融合した、京都の小さな宝庫です。古墳の存在や兼好法師の文学的足跡、平安貴族の別荘地という歴史の深さを感じつつ、街なかのオアシスとして気軽に訪れることができます。四季折々の花木と、展望の良さを活かした散策路は、地元市民や観光客にとっても癒しと学びの場として貴重な存在です。京都にお越しの際は、仁和寺参拝に合わせて散策に訪れてみると、また違った京都の風景と歴史に出会えることでしょう。双ヶ丘は子どもから高齢者まで親しまれている散策スポットであり、住民による散歩や親子の遊び場としても活用されています。ウェブ上の訪問者レビューには「住宅街に囲まれているのに“秘境”のようだ」「子供たちと歩くには程よい自然と運動量」といった声も多く、市民にとって貴重な緑地です。
双ヶ丘(雙ヶ岡、双ヶ岡)へ 京都市右京区
双ヶ丘(雙ヶ岡、双ヶ岡)へ 京都市右京区
ホームページ制作・修正、WEB制作関連について
新規ホームページの制作、ホームページリニューアルの相談先と無料相談

新規ホームページ制作やホームページリニューアルについてどこに相談すれば良いのか、誰に相談すれば良いのかというところはわかりにくいものです。
ホームページ制作やリニューアルの相談先として誰に相談すれば良いのか?という問題があります。
どのようにホームページを利用する予定かという点によって相談内容は大きく異なってきます。とりあえずホームページを公開するというものではなく、「とりあえず一つの販路としてホームページを活用する」という方針であるのならば、相談先はホームページ制作会社・Web制作会社以外の方が良いかもしれません。

「無料相談を実施しているホームページ制作会社、Web制作会社に相談してみよう」
というのは一つの方法です。
一方、コンサルタントの助言を得るという方法もあります。Webマーケティングなどの専業のコンサルタントだけでなく、全体的なマーケティング、経営コンサルタントに相談するという方法も一つです。
それではこうしたホームページの新規制作やリニューアルの相談、相談先について考えていきましょう。
ホームページ制作・リニューアルの無料相談と有料サポート
新規ホームページ制作やリニューアルの相談において、概要については無料でご相談に応じています。
Web制作会社はデザインや構造を含めて総合的な提案が可能です。外観上のデザインやSEOだけでなく、「見せ方」「導線設計」も含めたアプローチをしてくれる点が特徴です。「簡易診断」や「無料相談」に対応している業者であれば、初回ヒアリングで方向性を示してくれることもあります。費用をかける前に「この方向で進めて良いか」を確認できるのは大きなメリットです。
ホームページの新規制作やリニューアルを検討するとき、「どこに相談するのが正解なのか」と悩まれる方は少なくありません。見た目がきれいであれば良い、という時代はすでに過ぎ去り、今では実際にアクセスを集められるかどうか、成果に結びつく導線があるかどうかが、依頼先を決めるうえでの重要な判断材料となっています。さらに言えば、企業向けのBtoBビジネスと、個人のお客様を対象にしたBtoCビジネスでは、ホームページに求められる構造や訴求ポイントもまったく違ってきます。
そうした違いを踏まえ、相談先を選ぶ際には「無料相談」の場をどのように活用するかが、実は大きな分かれ道となるのです。単に制作の話だけに終わるのか、それとも検索エンジンからのアクセスやユーザー導線まで視野に入れて話をしてくれるか。この違いが後の集客成果に直結します。
新規ホームページ制作やホームページリニューアルについてどこに相談すれば良いのか、誰に相談すれば良いのかというところはわかりにくいものです。
ホームページ制作やリニューアルの相談先として誰に相談すれば良いのか?という問題があります。
どのようにホームページを利用する予定かという点によって相談内容は大きく異なってきます。とりあえずホームページを公開するというものではなく、「とりあえず一つの販路としてホームページを活用する」という方針であるのならば、相談先はホームページ制作会社・Web制作会社以外の方が良いかもしれません。
ホームページの無料相談において重視すべきWeb集客とWordPressを活用した総合的なマーケティング戦略
ホームページの無料相談は、単なるWebサイト制作の打ち合わせにとどまらず、企業や店舗のWeb集客の本質的な課題や将来的な展望までを俯瞰し、マーケティング戦略全体を見直す貴重な機会となります。特に中小企業や個人事業主の場合、広告・販促活動が限定的である一方、集客をWebに依存せざるを得ないという状況も多いため、この無料相談のフェーズでどこまで戦略を深掘りできるかが、今後のWeb集客成果を大きく左右します。
まず前提として、ホームページは単なる会社案内や情報掲載の場ではありません。目的に応じたアクセスを集め、その訪問者を見込み顧客へと転換し、最終的に売上へとつなげるマーケティングファネルの要であるべきです。したがって、無料相談の段階でヒアリングすべきなのは「どのような層のユーザーに来てほしいか」「どうやって見つけてもらいたいか」「何をもって成果とするのか」といった集客戦略上の設計意図です。
このとき、WordPressの採用は非常に理にかなった選択肢となります。WordPressは単なるコンテンツ管理システム(CMS)という枠を超えて、SEO施策の最適化、SNS連携、CTAボタンやランディングページの柔軟な構築、問い合わせ管理、EFO(入力フォーム最適化)、アクセス解析のタグ設置など、Webマーケティングの基盤機能をほぼ網羅できるプラットフォームとして活用できます。さらに、外部プラグインによって予約システム、メール配信、自動タグ挿入、スキーマ構造化対応まで幅広く対応可能であり、小規模事業者にとっては費用対効果の面でも優れた選択肢となります。
たとえば、集客をGoogle検索に頼るのであれば、SEOを意識したページ設計やカテゴリ構造、内部リンク設計、メタ情報の最適化などを視野に入れる必要があります。WordPressではAll in One SEOやRank Mathなどの拡張機能を利用することで、非エンジニアでも十分なSEO設定が可能となり、コンテンツマーケティングにも柔軟に対応できます。また、MEO(ローカルSEO)を強化したい場合は、Googleビジネスプロフィールと連携したアクセス導線の設計、地図・口コミ情報の埋め込み、地域名を意識した固定ページ・投稿ページの運用など、地域特化型サイトの設計も比較的容易に行えます。
加えて、SNSとの連動性もWordPressの強みです。InstagramやYouTube、X(旧Twitter)など、各SNSとの連携ウィジェットやOGP設定、埋め込みによる動的なフィード表示が可能であり、動画や写真コンテンツの更新とWeb上でのアーカイブ性を両立させることができます。特に近年は、SNS動画からの流入をLPに誘導し、そこからCVにつなげるという導線が重要視されています。この場合も、WordPressで動画連動型の特設ページ(ランディングページ)を構築し、リッチなビジュアルと直感的なアクション設計を組み込むことで、SNS起点のエンゲージメントをWeb上でしっかりと受け止めることが可能になります。
オフラインとの連携も、マーケティング視点での相談では欠かせません。たとえば、チラシやDM、店舗看板などの紙媒体にQRコードを設けてWordPressサイトのLPへ誘導することで、オフラインの見込み客をWeb上でのCVへとつなげる導線が設計できます。この場合、QRコード先のLPはキャンペーンや期間限定サービスに対応した構成とし、GoogleタグマネージャーやMetaピクセルを活用して効果測定を可能にしておくことが重要です。WordPress上でも、ABテストやヒートマップツール(Crazy Egg、Hotjarなど)との連携によって、ユーザーの行動解析を踏まえた改善がしやすくなります。
また、無料相談の段階でしばしば見落とされがちなのが、運用後のコンテンツ拡張性と更新体制です。一時的な集客ではなく、中長期的にアクセスを集めるためには、ニュースリリースやコラム、FAQ、事例紹介といった継続的な情報発信が欠かせません。WordPressではブログ投稿機能を活用して、スタッフでも更新可能な情報発信体制を整えることができますし、カテゴリやタグ機能を活用して、コンテンツの蓄積と整理もシステマティックに行えます。
このように、ホームページの無料相談は、見た目や料金の話に終始してしまうのではなく、自社のビジネス構造に合った集客戦略の構築と、それを支える実装基盤としてのWordPress活用方法まで視野に入れるべきです。SEO・MEO・SNS運用・チラシやDMとの連携、そして動画マーケティングやCRM(顧客管理)までを包括した設計ができるかどうかが、相談対応側の力量といえるでしょう。
WordPressという柔軟なプラットフォームを中心に据え、紙媒体やSNSといった周辺施策を統合することによって、ホームページは単なる案内板ではなく「集客の司令塔」へと進化します。そのためには、無料相談のフェーズで戦略的な問いかけを行い、企業ごとの現状・リソース・目標に応じたWeb活用の青写真を描く視点が欠かせません。
無料相談を実施しているホームページ制作会社、Web制作会社
「無料相談を実施しているホームページ制作会社、Web制作会社に相談してみよう」
というのは一つの方法です。
一方、コンサルタントの助言を得るという方法もあります。Webマーケティングなどの専業のコンサルタントだけでなく、全体的なマーケティング、経営コンサルタントに相談するという方法も一つです。
それではこうしたホームページの新規制作やリニューアルの相談、相談先について考えていきましょう。
ホームページ制作・リニューアルの無料相談と有料サポート
新規ホームページ制作やリニューアルの相談において、概要については無料でご相談に応じています。
Web制作会社はデザインや構造を含めて総合的な提案が可能です。外観上のデザインやSEOだけでなく、「見せ方」「導線設計」も含めたアプローチをしてくれる点が特徴です。「簡易診断」や「無料相談」に対応している業者であれば、初回ヒアリングで方向性を示してくれることもあります。費用をかける前に「この方向で進めて良いか」を確認できるのは大きなメリットです。
ホームページの新規制作やリニューアルを検討するとき、「どこに相談するのが正解なのか」と悩まれる方は少なくありません。見た目がきれいであれば良い、という時代はすでに過ぎ去り、今では実際にアクセスを集められるかどうか、成果に結びつく導線があるかどうかが、依頼先を決めるうえでの重要な判断材料となっています。さらに言えば、企業向けのBtoBビジネスと、個人のお客様を対象にしたBtoCビジネスでは、ホームページに求められる構造や訴求ポイントもまったく違ってきます。
そうした違いを踏まえ、相談先を選ぶ際には「無料相談」の場をどのように活用するかが、実は大きな分かれ道となるのです。単に制作の話だけに終わるのか、それとも検索エンジンからのアクセスやユーザー導線まで視野に入れて話をしてくれるか。この違いが後の集客成果に直結します。
ホームページ制作・修正、WEB制作関連について
京都市西京区にある月読神社(つきよみじんじゃ)。

月読神社境内は京都市指定史跡に指定されています。

松尾大社の南400メートルの場所にあります。
月読神社の京都への勧請に際しては秦氏など渡来系氏族の関わりがあったと考えられています。

月読神社は、式内社(名神大社)で現在は松尾大社摂社で「松尾七社」の一社です。境内には安産、縁結び、学問、航海安全、厄除けなど多様な御利益が期待できる祠があります。
月読神社(つきよみじんじゃ)
中にある月延石(つきのべいし)は、安産の神として信仰され「安産石」とも呼ばれています。神功皇后がこの石で腹をさすって安産したという伝承があり、以来「安産石」として信仰されています。
月読神社境内は京都市指定史跡に指定されています。
松尾大社の南400メートルの場所にあります。
月読神社の京都への勧請に際しては秦氏など渡来系氏族の関わりがあったと考えられています。
月読神社は、式内社(名神大社)で現在は松尾大社摂社で「松尾七社」の一社です。境内には安産、縁結び、学問、航海安全、厄除けなど多様な御利益が期待できる祠があります。
月読神社(つきよみじんじゃ)
中にある月延石(つきのべいし)は、安産の神として信仰され「安産石」とも呼ばれています。神功皇后がこの石で腹をさすって安産したという伝承があり、以来「安産石」として信仰されています。
ホームページ制作・修正、WEB制作関連について
ドメインとサーバーに関する費用。ドメインはインターネット上の住所のようなものす。ローマ字の文字列+.jpや.comのような文字列です。ドメインを取得して維持するために年間1,000円から3,000円程度の費用がかかります。ドメインは一度取得すれば毎年更新していきます。またホームページ必要なのがレンタルサーバーです。これはホームページのデータを保管するためのスペースです。国内で一般的な共有レンタルサーバーであれば、月額1,000円前後で安定した環境を確保することが可能です。信頼性や速度にこだわりたい場合は、もう少し上位のプランを選ぶ必要がありますが、創業初期であれば無理のないプランからスタートするのが現実的です。
特にWordPressを稼働させるためにはPHPやデータベースに対応したサーバーが必要です。
特にWordPressを稼働させるためにはPHPやデータベースに対応したサーバーが必要です。
ホームページ制作・修正、WEB制作関連について
WordPressテーマを購入して運用するのはいいが、生兵法は大怪我のもとである。
結局集客につながるかどうかは、テーマデザインの問題ではないからだ。

有料WordPressテーマ購入による自社サイト運用の不足点
「自社でWordPressテーマを使ってホームページ公開をするのとWeb制作会社にWordPressサイト制作を依頼するのとどっちが良いのだろう?」
企業が自社でレンタルサーバーを契約し、WordPressをインストールして有料WordPressテーマで企業ホームページを制作する」ということ自体には問題がない。
ただ、それ以外のところに問題が生じやすい。
ホームページの費用対効果を考えると、「費用は安くても効果がゼロ」なら、少ない費用すら無駄になるという事実がある。

企業の創業期において実用性と信頼性を両立させるために必要なWordPressサイト構成について。創業したばかりの時期にホームページを立ち上げる際、多くの方が「どこまで作り込むべきか」「どのページを用意すれば最低限の形になるのか」といった点が問題となります。限られた予算と時間の中で、すべてを理想どおりに整えるのは難しいとしても、一定の信頼性と情報の整理がされていれば、それだけで十分に企業としての存在感を伝えることが可能です。
まず最も大切なのは、訪問者にとって分かりやすく、かつ安心できる情報を掲載することです。どれほど凝ったデザインや動きのあるWordPressサイトであっても、肝心の情報が見当たらない、または信頼性を感じられない内容であれば、問い合わせや商談にはつながりません。初期段階では、シンプルで構いませんので、必要な情報を正しく配置することが求められます。
最初に整えておくべきはトップページです。トップページは企業の顔とも言える場所であり、どのようなビジネスをしているか、誰に向けてどのような価値を提供しているかを端的に伝える必要があります。ここでは、企業のコンセプトやサービス概要、対象となる顧客層、代表的な実績などを簡潔に紹介し、サイト内の他のページへの導線を明確に示すことが効果的です。

次に用意しておきたいのが、会社概要や事業案内にあたるページです。法人名や代表者名、所在地、設立年月日といった基本情報に加えて、どういった背景で事業を立ち上げたのか、どのような価値観でサービスを提供しているのかなどを明記することで、訪問者は企業の存在を具体的にイメージしやすくなります。また、電話番号やメールフォームなど、問い合わせ手段を明示しておくことで、信頼性も格段に向上します。
さらに、サービス紹介ページの設置も重要です。自社がどのような商品やサービスを提供しているかを具体的に記述することで、見込み客は「自分のニーズに合っているかどうか」を判断できます。価格帯や提供の流れ、納期の目安など、実際に依頼を検討している人が知りたい情報を想像しながら、丁寧に構成していくと良いでしょう。
また、写真や実績の掲載も可能であれば初期段階から意識したい要素です。施工事例や製品の写真、実際の作業風景などが掲載されていることで、サービスの信憑性や実行力を裏付ける材料となり、初めての訪問者にも安心感を与えることができます。画像は決して高価な撮影である必要はなく、スマートフォンで撮った自然な写真でも十分効果があります。ブログやお知らせといった更新情報のエリアも、簡単な形で導入しておくと良い効果が期待できます。創業直後は頻繁な更新が難しいかもしれませんが、事業の進捗やキャンペーン、新たなサービス展開などを定期的に記載していくことで、訪問者に対して「動いている会社」「継続的に活動している事業者」という印象を与えることができます。これは信頼性の面でも大きなポイントとなります。
WordPressサイトのスマートフォン対応も忘れてはならない項目です。現在では訪問者の多くがスマートフォンからアクセスしており、画面の見やすさや操作のしやすさが、そのまま滞在時間や問い合わせ率に直結します。WordPressであれば、ほとんどのテーマがモバイル対応を前提に設計されていますが、見え方や操作感は事前に確認しておくことが大切です。
このように、初期段階で用意すべきWordPressサイト構成は、決して多くのページ数を必要とするものではありません。むしろ、一つひとつのページにおいて伝えるべき情報が明確であり、来訪者にとって必要な導線が設計されていれば、数ページのシンプルな構成でも十分に事業を支えるホームページとして機能します。段階的に情報を増やし、コンテンツを洗練させていくための土台として、しっかりと基礎を整えておくことが、今後のサイト成長にとって極めて重要なのです。
ちょっとしたエラーすら修正できないからだ。
安く済ましたんなら安く済ましたなりにがんばれよ。
商品やサービスのYouTube動画を制作しGoogleやYahooの検索結果で上位表示させて集客
Google、Yahooで検索される際にYouTube動画を表示することで
今以上に新規顧客や売上を増やすことができます。
お困りごとがあればぜひお手伝いさせて頂ければ幸いです。
オウンドメディアのコンテンツに、私の持つライティングスキルがお力添えできる。
ライター不足でお悩みでしたら、ぜひ私に貴社オウンドメディアで執筆をさせていただけないでしょうか。すでにページ数が充実していても、リライトによるブラッシュアップもできます。
初稿提出後にクライアントから余白の調整など細かな部分でご指定
web制作・webシステム全般を得意としておりHTMLコーディング・サーバー移管やテスト検証など部分的な請負も可能。
結局集客につながるかどうかは、テーマデザインの問題ではないからだ。
有料WordPressテーマ購入による自社サイト運用の不足点
「自社でWordPressテーマを使ってホームページ公開をするのとWeb制作会社にWordPressサイト制作を依頼するのとどっちが良いのだろう?」
企業が自社でレンタルサーバーを契約し、WordPressをインストールして有料WordPressテーマで企業ホームページを制作する」ということ自体には問題がない。
ただ、それ以外のところに問題が生じやすい。
ホームページの費用対効果を考えると、「費用は安くても効果がゼロ」なら、少ない費用すら無駄になるという事実がある。
創業初期段階に必要なWordPressサイト構成
企業の創業期において実用性と信頼性を両立させるために必要なWordPressサイト構成について。創業したばかりの時期にホームページを立ち上げる際、多くの方が「どこまで作り込むべきか」「どのページを用意すれば最低限の形になるのか」といった点が問題となります。限られた予算と時間の中で、すべてを理想どおりに整えるのは難しいとしても、一定の信頼性と情報の整理がされていれば、それだけで十分に企業としての存在感を伝えることが可能です。
まず最も大切なのは、訪問者にとって分かりやすく、かつ安心できる情報を掲載することです。どれほど凝ったデザインや動きのあるWordPressサイトであっても、肝心の情報が見当たらない、または信頼性を感じられない内容であれば、問い合わせや商談にはつながりません。初期段階では、シンプルで構いませんので、必要な情報を正しく配置することが求められます。
最初に整えておくべきはトップページです。トップページは企業の顔とも言える場所であり、どのようなビジネスをしているか、誰に向けてどのような価値を提供しているかを端的に伝える必要があります。ここでは、企業のコンセプトやサービス概要、対象となる顧客層、代表的な実績などを簡潔に紹介し、サイト内の他のページへの導線を明確に示すことが効果的です。
次に用意しておきたいのが、会社概要や事業案内にあたるページです。法人名や代表者名、所在地、設立年月日といった基本情報に加えて、どういった背景で事業を立ち上げたのか、どのような価値観でサービスを提供しているのかなどを明記することで、訪問者は企業の存在を具体的にイメージしやすくなります。また、電話番号やメールフォームなど、問い合わせ手段を明示しておくことで、信頼性も格段に向上します。
さらに、サービス紹介ページの設置も重要です。自社がどのような商品やサービスを提供しているかを具体的に記述することで、見込み客は「自分のニーズに合っているかどうか」を判断できます。価格帯や提供の流れ、納期の目安など、実際に依頼を検討している人が知りたい情報を想像しながら、丁寧に構成していくと良いでしょう。
また、写真や実績の掲載も可能であれば初期段階から意識したい要素です。施工事例や製品の写真、実際の作業風景などが掲載されていることで、サービスの信憑性や実行力を裏付ける材料となり、初めての訪問者にも安心感を与えることができます。画像は決して高価な撮影である必要はなく、スマートフォンで撮った自然な写真でも十分効果があります。ブログやお知らせといった更新情報のエリアも、簡単な形で導入しておくと良い効果が期待できます。創業直後は頻繁な更新が難しいかもしれませんが、事業の進捗やキャンペーン、新たなサービス展開などを定期的に記載していくことで、訪問者に対して「動いている会社」「継続的に活動している事業者」という印象を与えることができます。これは信頼性の面でも大きなポイントとなります。
WordPressサイトのスマートフォン対応も忘れてはならない項目です。現在では訪問者の多くがスマートフォンからアクセスしており、画面の見やすさや操作のしやすさが、そのまま滞在時間や問い合わせ率に直結します。WordPressであれば、ほとんどのテーマがモバイル対応を前提に設計されていますが、見え方や操作感は事前に確認しておくことが大切です。
このように、初期段階で用意すべきWordPressサイト構成は、決して多くのページ数を必要とするものではありません。むしろ、一つひとつのページにおいて伝えるべき情報が明確であり、来訪者にとって必要な導線が設計されていれば、数ページのシンプルな構成でも十分に事業を支えるホームページとして機能します。段階的に情報を増やし、コンテンツを洗練させていくための土台として、しっかりと基礎を整えておくことが、今後のサイト成長にとって極めて重要なのです。
自力のWordPress運営
自力のWordPress運営で躓くケースが多いような気がする。ちょっとしたエラーすら修正できないからだ。
WordPressのことをただで聞こうとする客
WordPressのことをただで聞こうとする客が増えた。安く済ましたんなら安く済ましたなりにがんばれよ。
誰でも作れるWordPress
「誰でも作れるWordPress」ということは優位性が生み出しにくいということになる。二転三転するホームページ制作
ホームページ制作において制作内容が二転三転する場合、主に中心となる目的が確定していないことが原因となっている。意志決定の部分で軸がないと話が二転三転しやすい。商品やサービスのYouTube動画を制作しGoogleやYahooの検索結果で上位表示させて集客
Google、Yahooで検索される際にYouTube動画を表示することで
今以上に新規顧客や売上を増やすことができます。
ホームページ制作の準備
ホームページ制作の準備として、明確なサイトのコンセプト、ターゲットの選定、サイト構造の設計から始める必要がある。「コーダーがちょうど抜けてしまった」、「人手不足で案件の受注ができない」などのお困りごとがあればぜひお手伝いさせて頂ければ幸いです。
オウンドメディアのコンテンツに、私の持つライティングスキルがお力添えできる。
ライター不足でお悩みでしたら、ぜひ私に貴社オウンドメディアで執筆をさせていただけないでしょうか。すでにページ数が充実していても、リライトによるブラッシュアップもできます。
初稿提出後にクライアントから余白の調整など細かな部分でご指定
web制作・webシステム全般を得意としておりHTMLコーディング・サーバー移管やテスト検証など部分的な請負も可能。
ホームページ制作・修正、WEB制作関連について
サブスクホームページ(月額料金制)の概要とメリット・デメリット

サブスクホームページ(月額料金制)利用の判断基準
ホームページ制作・作成サービスの中にはサブスクホームページ(月額料金制)があります。
メリットとして初期費用は0または低料金でスタートすること可能。
毎月の月額料金だけでホームページ制作・運営が可能であることが特徴です。
一般のホームページ制作と比較して制作の初期コストが低く失敗して別のものに切り替える時に切り替えやすいという面もありますが、最低契約期間の設定がある場合もあります。
デメリットは中長期運用の場合トータルコストが高く、また、Web集客・マーケティング効果を得にくいという点、SEO・アクセス面で難点があるという点が挙げられます。
サブスクホームページ(月額料金制)を利用するかどうか判断基準は「ホームページ利用目的」です。単に公開したいだけなのか、ホームページを利用した本格的なWebマーケティングを実施する予定かという意図の違いが判断基準となります。
月額定額制(サブスク)ホームページのメリット・デメリット

ホームページ制作の形態が多様化しています。初期費用を抑えられる「サブスクリプション型(月額制)」のホームページ制作サービスがあります。初期コストが抑えられる、定額で運用できる、手軽に始められるといったメリットが訴求され中小企業や個人事業主の間で広く利用されることがあります。しかしながら、「月額いくらでホームページが作れる」「無料でスタートできる」といった制作開始時の条件ばかりに目を向けて契約してしまい、運用が始まってから問題が出てくる場合があります。契約内容によっては、月額料金に含まれる更新作業に「月◯回まで」「文章数◯文字以内」などの細かな制限がある場合があります。意外と見落とされがちなのが、「契約中のホームページは誰のものか?」という点です。サブスクリプションホームページでは、制作したホームページの著作権やデータが制作会社側に帰属するケースがあります。
サブスクホームページ(月額料金制)利用の判断基準
ホームページ制作・作成サービスの中にはサブスクホームページ(月額料金制)があります。
メリットとして初期費用は0または低料金でスタートすること可能。
毎月の月額料金だけでホームページ制作・運営が可能であることが特徴です。
一般のホームページ制作と比較して制作の初期コストが低く失敗して別のものに切り替える時に切り替えやすいという面もありますが、最低契約期間の設定がある場合もあります。
デメリットは中長期運用の場合トータルコストが高く、また、Web集客・マーケティング効果を得にくいという点、SEO・アクセス面で難点があるという点が挙げられます。
サブスクホームページ(月額料金制)を利用するかどうか判断基準は「ホームページ利用目的」です。単に公開したいだけなのか、ホームページを利用した本格的なWebマーケティングを実施する予定かという意図の違いが判断基準となります。
月額定額制(サブスク)ホームページのメリット・デメリット
運用が始まってから問題が出てくるサブスクリプションホームページ
ホームページ制作の形態が多様化しています。初期費用を抑えられる「サブスクリプション型(月額制)」のホームページ制作サービスがあります。初期コストが抑えられる、定額で運用できる、手軽に始められるといったメリットが訴求され中小企業や個人事業主の間で広く利用されることがあります。しかしながら、「月額いくらでホームページが作れる」「無料でスタートできる」といった制作開始時の条件ばかりに目を向けて契約してしまい、運用が始まってから問題が出てくる場合があります。契約内容によっては、月額料金に含まれる更新作業に「月◯回まで」「文章数◯文字以内」などの細かな制限がある場合があります。意外と見落とされがちなのが、「契約中のホームページは誰のものか?」という点です。サブスクリプションホームページでは、制作したホームページの著作権やデータが制作会社側に帰属するケースがあります。
ホームページ制作・修正、WEB制作関連について
ホームページの調査・診断・改善提案

「ホームページについて調査や診断をして欲しい」
サーバー内部のファイルチェック、簡易エラーチェック、軽微な改善点のご案内
「ホームページの改善提案が欲しい」
ホームページ全体を概観し、ご利用目的と照らし合わせて重要度の高い「改良が必要な部分」をリストアップ
ホームページに関する各種更新や安全な削除など、様々な修正・改良策の可否の判断には、事前に入念な調査や診断が必要になる場合があります。無料提案や無料相談は営業行為に偏るか、提案や相談が自社サービスの利用に繋がらず企業が存続できなくなります。こうしたことから一般的には、無料の提案や相談は、最終的に自社サービスの売り込みに繋げざるを得ません。
そうした視点を排除したご利用者様にとって本当に必要な施策に目を向けるために、サポート・ご相談サービス。
サポートサービス|調査・診断・改善提案・SEO簡易分析・Web全般のご相談
タイトル・メタ情報 ページごとに最適化されているか
モバイル対応 モバイルフレンドリーかどうか
ページ速度 表示が遅すぎないか
インデックス状況 Googleに正しく登録されているか
内部リンク 情報が整理されているか、構造は最適か
「ホームページについて調査や診断をして欲しい」
サーバー内部のファイルチェック、簡易エラーチェック、軽微な改善点のご案内
「ホームページの改善提案が欲しい」
ホームページ全体を概観し、ご利用目的と照らし合わせて重要度の高い「改良が必要な部分」をリストアップ
ホームページに関する各種更新や安全な削除など、様々な修正・改良策の可否の判断には、事前に入念な調査や診断が必要になる場合があります。無料提案や無料相談は営業行為に偏るか、提案や相談が自社サービスの利用に繋がらず企業が存続できなくなります。こうしたことから一般的には、無料の提案や相談は、最終的に自社サービスの売り込みに繋げざるを得ません。
そうした視点を排除したご利用者様にとって本当に必要な施策に目を向けるために、サポート・ご相談サービス。
サポートサービス|調査・診断・改善提案・SEO簡易分析・Web全般のご相談
タイトル・メタ情報 ページごとに最適化されているか
モバイル対応 モバイルフレンドリーかどうか
ページ速度 表示が遅すぎないか
インデックス状況 Googleに正しく登録されているか
内部リンク 情報が整理されているか、構造は最適か
ホームページ制作・修正、WEB制作関連について
ホームページ修正依頼方法「伝えにくい具体的な修正内容のご連絡方法」
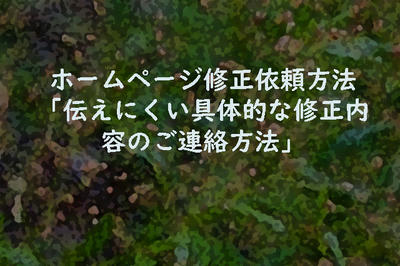
ホームページ修正ご依頼時の修正内容のご連絡方法は、原則メール内文章でご連絡いただいておりますが、メール文章での表現が難しい場合は、キャプチャ画像を送付いただく形など様々な形でご対応しております。修正対象ページをスクリーンショット(キャプチャ)で保存いただき、修正箇所に印を入れていただく方法があります。
また、該当ページをプリントアウトした上で手書きで修正内容を記載いただいたき、そのプリントを画像としてお送りいただく形でも対応しています。

ホームページ制作会社に「簡単に編集できます」と説明されたにもかかわらず、実際にはCMSのログイン権限が提供されておらず、すべての変更作業を制作会社に依存せざるを得ないケースもあります。あるいは、編集可能な部分がごく限定されていて、運用上不便に感じるケースも見受けられます。
そうした場合はホームページを移管する提案をする場合があります。
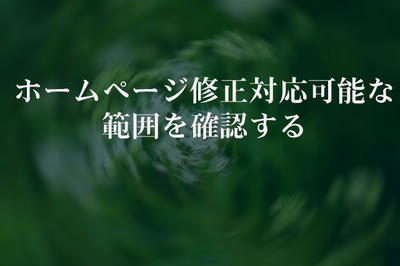
ホームページ修正ご依頼時の修正内容のご連絡方法は、原則メール内文章でご連絡いただいておりますが、メール文章での表現が難しい場合は、キャプチャ画像を送付いただく形など様々な形でご対応しております。修正対象ページをスクリーンショット(キャプチャ)で保存いただき、修正箇所に印を入れていただく方法があります。
また、該当ページをプリントアウトした上で手書きで修正内容を記載いただいたき、そのプリントを画像としてお送りいただく形でも対応しています。
最初に修正するホームページのURL(修正対象ページのURL)と、修正にかかるご要望(修正内容)をお伝え下さい。修正対象ホームページならびに修正対象となる具体的なページを確認させていただき、ご希望の修正内容を把握させていただきます。
ホームページの修正に関する各種ログイン情報、WebサーバーのFTP情報やWordPress等のログイン情報が不明な場合はお取り扱いできない場合がございますが、調査方法等につきましてご案内させていただくことも可能です。
ホームページ修正のご依頼方法と修正時の代替案ご案内例
ホームページ修正のご依頼方法と修正時の代替案ご案内例
ホームページ修正ができない場合の提案
ホームページ制作会社に「簡単に編集できます」と説明されたにもかかわらず、実際にはCMSのログイン権限が提供されておらず、すべての変更作業を制作会社に依存せざるを得ないケースもあります。あるいは、編集可能な部分がごく限定されていて、運用上不便に感じるケースも見受けられます。
そうした場合はホームページを移管する提案をする場合があります。
ホームページ修正対応可能な範囲を確認する
「ホームページ修正は、どんな修正でも依頼すればやってくれる」と思いがちですが元のホームページ契約形態によって対応範囲が異なる場合があります。
契約が「更新対応込み」なのか「制作のみで保守なし」なのか
WordPressなどのCMS更新作業が含まれるかどうか
デザインや画像の作り直しが別途費用になるかどうか
と言った点や、そもそもサーバー情報が公開されない場合もあります。
と言った点や、そもそもサーバー情報が公開されない場合もあります。
ホームページ制作・修正、WEB制作関連について
少ないアクセスでも問い合わせが来るホームページ集客方法。ホームページ集客における内容の充実の重要性、検索順位やアクセス数にこだわらずホームページ集客を実践する方法について。
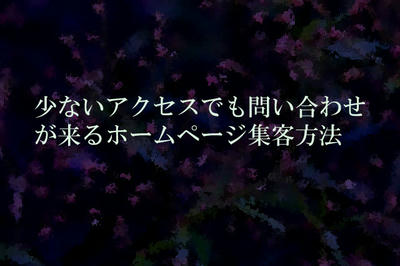
新規ホームページ制作を実施しても構いませんが自社で更新しやすいWordPressサイトなどに変更した方が、中長期的には理に適っている場合があります。そうしたホームページの内容を充実させるページづくりや全体の企画を作ることが難しい場合は、Webコンサルティングなどを利用するとよいでしょう。
アクセス数にこだわらずホームページを制作し、必要なページを丹念に作り、多少のアクセスがあればホームページ集客を実践することができます。
ホームページ集客の実践として検索順位やアクセス数、SEOを考える前に内容の充実の方に意識を向け、ホームページを運営する企業が「どのようにしてメッセージを伝えるか?」ということを考えることが大切。重要であるのはページ内容であるため、新規ホームページ制作や大幅なリニューアルは必要なく、既存ホームページの改良で十分です。ページ内容を充実させるということは、キーワードが増えることにも繋がり、検索エンジンを経由してアクセスがやってくる可能性も高まります。
ホームページ集客 メッセージと接点
Web集客・ホームページ集客の方法の基本的なポイントは、対象者に対してサービスやメッセージを用意することと、その対象者との接点を作ること。ホームページ集客における内容の充実の重要性はかなり高く、これができれば少ないアクセスでも結果を出すことができます。数値化しにくく可視化しにくいという点もありますが、これはホームページ関連の事業者や広告収入を目的としているサイト運営者があまり気にしない点です。それは単純にホームページという枠組みを超えたマーケティングのあり方です。
ホームページ集客の実践 少ないアクセスでも結果を出す方法見込み客の心を動かすホームページ内容
検索順位やアクセス数にこだわらずCV(コンバージョン)、問い合わせを得るにはどうすればよいか?それは、ホームページ内容の充実によって「見込み客の心が動くこと」新規ホームページ制作を実施しても構いませんが自社で更新しやすいWordPressサイトなどに変更した方が、中長期的には理に適っている場合があります。そうしたホームページの内容を充実させるページづくりや全体の企画を作ることが難しい場合は、Webコンサルティングなどを利用するとよいでしょう。
アクセス数にこだわらずホームページを制作し、必要なページを丹念に作り、多少のアクセスがあればホームページ集客を実践することができます。
ホームページ集客の実践として検索順位やアクセス数、SEOを考える前に内容の充実の方に意識を向け、ホームページを運営する企業が「どのようにしてメッセージを伝えるか?」ということを考えることが大切。重要であるのはページ内容であるため、新規ホームページ制作や大幅なリニューアルは必要なく、既存ホームページの改良で十分です。ページ内容を充実させるということは、キーワードが増えることにも繋がり、検索エンジンを経由してアクセスがやってくる可能性も高まります。
ホームページ制作・修正、WEB制作関連について
WordPressサイト上のテーマカスタマイズや、追加プラグインによるWordPressカスタマイズ、WordPressサイトのエラーに関する各種修正・サイト復旧など
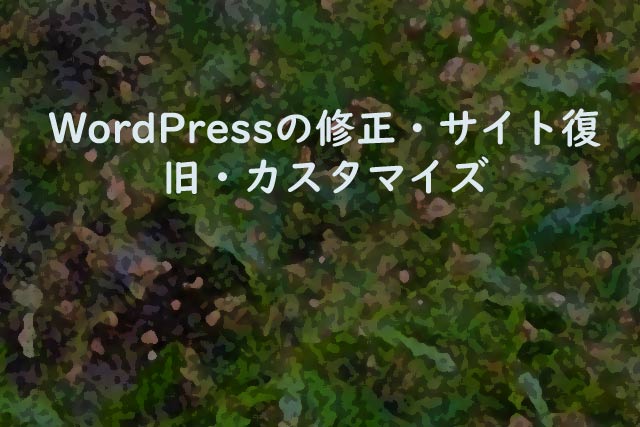
WordPressの修正・カスタマイズ
特殊なテンプレートを作成すればある程度は自由が叶うが、基本的なテーマのままの場合、一定以上を望んだ場合制限が出てくる。
WordPressが真っ白になる現象は、突然発生するものですが、その多くは定期的なバックアップやテスト環境での動作確認といった予防策により回避可能です。
最低限しておきたい予防策
定期バックアップ(自動+手動)
テーマやプラグインの更新はまずテスト環境で
FTP接続やサーバーパネルのアクセス情報を控えておく
メールフォームや決済機能の動作確認を定期的に行う
WordPressの修正・カスタマイズ
WordPressによる制限
WordPressにも制限がある。会員制サイトを作る際などは細かな制限が気になる場合もあるだろう。特殊なテンプレートを作成すればある程度は自由が叶うが、基本的なテーマのままの場合、一定以上を望んだ場合制限が出てくる。
WordPressが真っ白になる現象は、突然発生するものですが、その多くは定期的なバックアップやテスト環境での動作確認といった予防策により回避可能です。
最低限しておきたい予防策
定期バックアップ(自動+手動)
テーマやプラグインの更新はまずテスト環境で
FTP接続やサーバーパネルのアクセス情報を控えておく
メールフォームや決済機能の動作確認を定期的に行う
ホームページ制作・修正、WEB制作関連について
Webコンサルティングとは
Webコンサルティングとは、提案から制作・更新まで一貫して クライアントビジネスに有益な成果を出すために、 Webサイトの可能性を最大限に引き出すサービスです。検索上位を狙うには、Webマーケティングを取り入れたコンサルティングは不可欠です。コンサルティング」と聞くと信用できないような言葉のイメージがあり、コンサルティング会社から提示される実績もどこまで「本当の実績」なのかわからない場合があります。
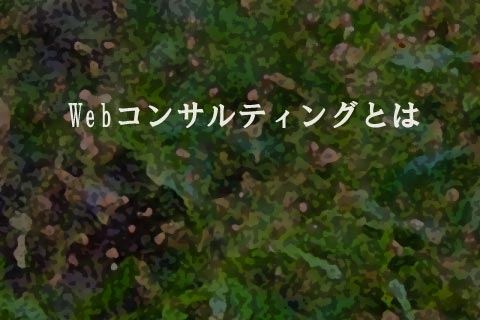
専門に特化するのではなく、トータルで支援をするという意味で「Webコンサルタント」Webコンサルティングサービスとウェブ解析レポート作成サービスをご用意Webコンサルティングは総合力に定評があります。売上の基盤となる広告施策を軸に、広告を成功させるためのホームページ制作WebコンサルティングとはWeb上でいかに人を集めるか。購入契約率を高めるか。
Webマーケティングを取り入れたコンサルティングは不可欠

コンサルティングって何をしてくれるの? コンサルタント訪問、コンサルタント打ち合わせ、コンサルタント説明いかにリピート率を高められるか?という仕組みを作るために、Webコンサルタントが分析診断を行い、戦略的なWebマーケティングを通じて、有効な施策を実施。事業の位置付け、集客手法などコストと利益を試算しながら進めます。
Webコンサルティング
Webコンサルティングとは、提案から制作・更新まで一貫して クライアントビジネスに有益な成果を出すために、 Webサイトの可能性を最大限に引き出すサービスです。検索上位を狙うには、Webマーケティングを取り入れたコンサルティングは不可欠です。コンサルティング」と聞くと信用できないような言葉のイメージがあり、コンサルティング会社から提示される実績もどこまで「本当の実績」なのかわからない場合があります。
専門に特化するのではなく、トータルで支援をするという意味で「Webコンサルタント」Webコンサルティングサービスとウェブ解析レポート作成サービスをご用意Webコンサルティングは総合力に定評があります。売上の基盤となる広告施策を軸に、広告を成功させるためのホームページ制作WebコンサルティングとはWeb上でいかに人を集めるか。購入契約率を高めるか。
Webマーケティングを取り入れたコンサルティングは不可欠
コンサルティングって何をしてくれるの? コンサルタント訪問、コンサルタント打ち合わせ、コンサルタント説明いかにリピート率を高められるか?という仕組みを作るために、Webコンサルタントが分析診断を行い、戦略的なWebマーケティングを通じて、有効な施策を実施。事業の位置付け、集客手法などコストと利益を試算しながら進めます。
Webコンサルティング
ホームページ制作・修正、WEB制作関連について
WordPressでホームページを制作することのメリット
WordPressのメリットとデメリット
無料で簡単にホームページやブログが作成できるWordpress(ワードプレス)WordPressでホームページ制作することのメリットは、企業のWebマーケティングに使うホームページとして、コンテンツの追加や編集といったホームページの更新を自社管理できること。
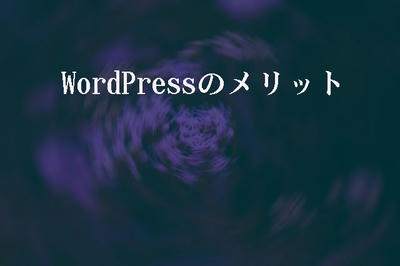
WordPressは豊富なプラグインと高いカスタマイズ性を備え、初心者でも使いやすいのがメリット。
ただ、デメリットとして、保守がうまくいかなかったりプラグインが動作停止したり、といったときには自己責任となる。本体、テーマ、プラグイン、そしてサーバーのphpバージョン等々いろんなバージョンが変わるからなぁ。
アップデートは楽だが、バージョンダウンは面倒であるため、少し様子を見たほうがいい場合がある。
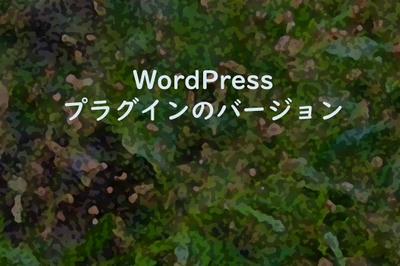
WordPressのメリットとデメリット
無料で簡単にホームページやブログが作成できるWordpress(ワードプレス)WordPressでホームページ制作することのメリットは、企業のWebマーケティングに使うホームページとして、コンテンツの追加や編集といったホームページの更新を自社管理できること。
WordPressは豊富なプラグインと高いカスタマイズ性を備え、初心者でも使いやすいのがメリット。
ただ、デメリットとして、保守がうまくいかなかったりプラグインが動作停止したり、といったときには自己責任となる。本体、テーマ、プラグイン、そしてサーバーのphpバージョン等々いろんなバージョンが変わるからなぁ。
WordPress プラグインのバージョン
WordPressのプラグインのバージョンは、機能やセキュリティの面では最新であるに越したことはないが、有料化のために、無料時の機能が消えている場合があるのでアップデートしないほうが良い場合もある。アップデートは楽だが、バージョンダウンは面倒であるため、少し様子を見たほうがいい場合がある。
ホームページ制作・修正、WEB制作関連について
国指定の名勝双ヶ丘(ならびがおか、正式名称は雙ヶ岡)。雙ヶ岡の表記は、双ヶ丘、双ヶ岡、双岡、並岡、雙丘、双岳とたくさんあります。

双ヶ丘(ならびがおか、雙ヶ岡、双ヶ岡))は、北から順に一の丘(いちのおか)、二の丘(にのおか)、三の丘(さんのおか)と丘が並んでいます。
双ヶ丘(雙ヶ岡、双ヶ岡)の標高は、一の丘(標高116メートル)、二の丘(標高102メートル)、三の丘(標高78メートル)。古墳は、総称して双ヶ岡古墳群と呼ばれています。京都市右京区
双ヶ丘(雙ヶ岡、双ヶ岡)
双ヶ丘(雙ヶ岡、双ヶ岡)へ 京都市右京区双ヶ丘(ならびがおか、雙ヶ岡、双ヶ岡))は、北から順に一の丘(いちのおか)、二の丘(にのおか)、三の丘(さんのおか)と丘が並んでいます。
双ヶ丘(雙ヶ岡、双ヶ岡)の標高は、一の丘(標高116メートル)、二の丘(標高102メートル)、三の丘(標高78メートル)。古墳は、総称して双ヶ岡古墳群と呼ばれています。京都市右京区
ホームページ制作・修正、WEB制作関連について
フリーエリア
DTM
WEB
ホームページ制作
最新記事
(12/13)
(10/20)
(09/16)
(09/03)
(08/22)
(08/18)
(08/18)
(08/16)
(07/30)
(07/22)
(07/17)
(07/11)
(07/05)
(07/03)
(06/23)
(06/08)
(06/02)
(05/21)
(05/20)
(05/09)
(04/05)
(03/23)
(03/15)
(03/03)
(03/02)
プロフィール
HN:
usamaru
性別:
非公開
ブログ内検索
アーカイブ
最古記事
(02/04)
(03/07)
(04/09)
(06/17)
(07/29)
(10/31)
(12/03)
(01/19)
(01/24)
(01/24)
(01/24)
(02/09)
(08/13)
(09/13)
(06/25)
(08/10)
(08/12)
(11/01)
(11/30)
(05/03)
(07/15)
(01/07)
(01/19)
(01/24)
(03/13)
